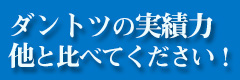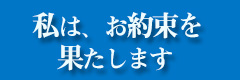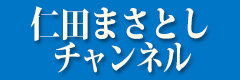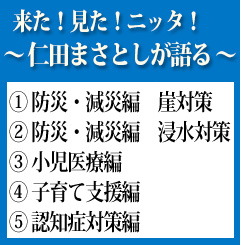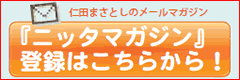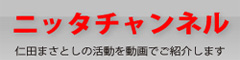- 横浜市会議員 公明党所属 仁田まさとし
- シャープな感性、ホットな心 仁田まさとしの議員活動をご報告します。
メールマガジン
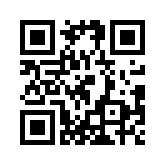
メールマガジンの登録
nitta-ctl@labo2.sere.jpへ空メールを送信します。登録完了メールを受信できれば、登録完了です
※携帯電話で受信者設定を指定している場合は、「labo2.sere.jp」からのメールを受信できるように、必ず受信者設定を行ってください。
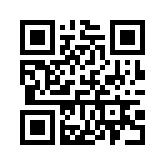
メールマガジンの解除
nitta-admin@labo2.sere.jpへ空メールを送信します。※解除には数日かかる場合があります。ご了承ください。
仁田まさとしメールマガジン
ニッタ マガジン Vol.695 2024.07.22
「健康」に関する3話
このほど横浜市より発表された「健康」に関する話題の中から3つをご紹介します。
一つ目は、市民意識調査です。
1月に行われた健康に関する市民意識調査の結果が公表されました。
今回、新しく調査項目に加えられた中にも示唆に富むものがあります。
ヒートショックについて、言葉も意味も知っていると回答した人の割合は85.9%と認知度は高い結果。しかし不慮の事故で亡くなる方は多いため、予防方法を実践できるよう啓発が必要です。
「ヘモグロビンエーワンシー(HbA1c)」について、聞いたことがあり、意味も知っている人の割合は22.4%。これは糖尿病に関連した血液検査で、結果に応じた生活習慣の改善・早期受診・継続治療において特に重要であり、周知・啓発が必要です。
自身の生活習慣の改善について、「関心がない」「改善は必要だが、今すぐ変えるつもりはない」と答えた人の割合は35.2%。「健康に望ましい行動をとりやすく環境づくり」が必要です。
二つ目は、「はまの元気ごはん弁当」です。
横浜市が定める「栄養バランスのよい1食あたりの栄養価の基準」を満たした「ハマの元気ごはん弁当」を、相鉄ローゼン株式会社やイオンリテール株式会社が横浜市と連携して企画・販売しています。栄養バランスのよい食事を自然に選択できる食環境づくりの取組です。
三つ目は、健康イベントの開催です。
8月8日(木)11時から16時まで、横浜市役所(アトリウムほか)で、横浜市立大学の学生が発案した「考えよう、健康。延ばそう、健康寿命」との健康課題に迫るイベントが開催されます。
体験型の健康測定ブースや健康を身近に感じるパネルディスカッション等が予定されています。
仁田まさとしは、市民の健康づくりを推進します。
ニッタ マガジン Vol.694 2024.07.15
帯状疱疹ワクチンは定期接種が妥当と
6月に開かれた厚生労働省の専門委員会において、帯状疱疹ワクチンは「定期接種化することが妥当」との評価が示されました。
帯状疱疹は、水痘(水ぼうそう)のウイルスが神経に潜み続け、加齢や疲労、ストレスなどによって免疫機能が低下することでウイルスが再び目覚め、帯状疱疹として発症します。発症率は50歳代から上昇し、80歳までに3人に1人が発症すると言われています。
このウイルスは、神経を傷つけながら皮膚に向うため、多くは皮膚症状が現れる数日前に痛みが生じます。その後発疹や水ぶくれが帯状に現れ痛みが強くなり、生活の質が低下するなど日常生活に大きく影響を及ぼします。
また、50歳以上の患者の約2割が、痛みが残る帯状疱疹後神経痛(PHN)に移行するとされています。
帯状疱疹の予防にはワクチンが有効ですが、高い予防効果の組換えワクチンの接種には4万円超の費用(2回分)が掛かり、公費助成を可能とする定期接種化を望む声が多く寄せられてきました。
公明党市議団は令和4年10月に山中竹春市長に対し定期接種化を国に働きかけるよう要望し、同年12月に厚労省へ要望されました。また、横浜市では、令和5年に国保データにより罹患状況を調査し結果を厚労省へ提供しました。さらに令和6年度には社会保険データによる調査を加え全年齢層の状況を分析予定です。
このような中、平成30年の厚生科学審議会以降、議論が進んでいない状況でしたが、昨年11月に5年ぶりに議論が再開され、本年6月の同審議会予防接種・ワクチン分科会において、「定期接種化」との方針に至りました。
今後は、対象年齢など具体的な運用について、予防接種基本方針部会で検討されます。
仁田まさとしは、“帯状疱疹に負けない横浜”を目指します。
ニッタ マガジン Vol.693 2024.07.08
京都市の高校教育改革に学ぶ
このほど、京都市教育委員会事務局及び京都市立堀川高校を訪問し、教育改革への意見交換と「堀川の奇跡」を起こした「探究」の現場を視察する機会を得ました。
京都市教育委員会事務局で準備頂いた資料には瞠目すべき一頁がありました。
「『今』、京都市立高校は大きな改革期にあります。」と。
京都市教育委員会では、市立高校総体の社会的役割や存在意義などの指針として定めたスクールミッションを踏まえて各学校がスクールポリシーを策定し、不断の点検・見直しを行っています。
「設置義務のない京都市が高校を設置する使命・役割」を念頭に意見交換しましたが、「先進的で魅力ある教育を創造・実践・発信し、いつの時代も市民に信託される学校」とのスクールミッションにその解をみることができました。
また、改革の基には、「京都市立高校21世紀構想委員会」の3次にわたる答申がありました。
特に、第2次答申では、「新たな堀川高校において、活字離れや理科・数学離れなどの今日的課題に対応するため、人間とその営みについて学び、自然について学ぶ新しい専門学科を創設したい」と、堀川高校を構想のパイロット校として、理念の具体化を図ることが盛り込まれ、人間探究科と自然探究科が創設されました。
昨年には、開建高校、美術工芸高校が設置されましたが、これまで、普通科だけでなく、探究、工業、美術、音楽など多彩な専門学科が設置されています。
堀川高校の「探究」の授業を視察した際には、「すべては君の『知りたい』からはじまる」とし、高校卒業後に自ら研究を進める姿勢や能力を養い「自立する18歳を育む」との目標が実感を持って迫ってきました。
仁田まさとしは、市立高校の「探究」に取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.692 2024.07.01
パーキング・パーミット制度が開始
先週26日に山中横浜市長は記者会見において、「横浜市パーキング・パーミット制度の導入」を発表しました。
パーキング・パーミット制度とは、利用対象者が「車いす使用者用駐車区画」や「優先駐車区画」に駐車する際に、横浜市が発行した利用証を掲示することで、安心して駐車できるようにするとともに、適正な利用を推進する制度です。
これまで、「車いす使用者用駐車区画」の利用について、車いす使用者の方や、外見からはわかりにくい障がいのある方、妊産婦の方など、移動に配慮が必要な方から、安心して駐車したいというお声が寄せられていました。
例えば、「病気で歩くのが大変なのですが、外見上ではわからないため、後ろめたい気持ちで車いす用の駐車場を利用しています。」「妊娠中なので、車いす用の駐車場を使用できると助かります。」などです。
利用対象者は、歩行が困難または移動に配慮が必要な高齢者や障がい者等、およそ30万人です。
要件としては、高齢者は要介護認定者、障がい者は等級によります。難病患者は受給者証の取得者。妊産婦は母子手帳取得時から産後1年まで。けがをされた方は医師の診断書によります。
申請受付は本日より開始され、電子申請または郵送となります。利用証は順次発送され、お手元に届いたときから「車いす使用者用駐車区画」等に駐車できます。
令和5年3月8日の市会健康福祉・医療常任委員会で、横浜市に「パーキング・パーミット制度」を導入すべきと提案しました。
今後は、幅の広い「車いす使用者用駐車区画」に加えて、幅は広くないものの、建物の出入り口近くに設置される「優先駐車区画」の確保が求められます。
仁田まさとしは、インクルーシブなまちづくりに取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.691 2024.06.24
保健と介護予防の一体で自立支援
本年度から、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」として、糖尿病・循環器疾患等の重症化予防やフレイル予防を図る事業が、地元南区を含む市内3区で、先行的に展開されます。
フレイルとは、「年齢を重ねたり、病気になったりすることで、体力や気力、認知機能など、からだとこころの機能が低下し、将来介護が必要になる危険性が高くなっている状態」をいいます。
令和4年の調査によると、介護が必要となった主な原因は「脳血管疾患」「関節疾患」「骨折・転倒」が上位でした。
この事業により、高血圧症、糖尿病、虚血性心疾患の合併が多い「脳血管疾患」に対しては重症化予防の取組が、「関節疾患」「骨折・転倒」に対しては身体的フレイル予防の取組による効果が期待できます。
そのために、脳血管疾患を含めた糖尿病・循環器疾患等の重症化予防や、身体的フレイル・身体的フレイルと関係の深い低栄養や口腔機能低下のリスクがある後期高齢者を支援するハイリスクアプローチと、前期高齢者も含めた幅広い啓発等を民間企業等と連携するポピュレーションアプローチが実施されます。
ハイリスクアプローチの対象者は国民健康保険情報等から把握され、案内を発送し同意が得られた方に対して医療専門職による訪問支援や民間事業者との連携による通所型集団支援が行われます。
ポピュレーションアプローチの対象者へは高齢者対象の地域の通いの場等でフレイル予防等の普及啓発や健康教育・健康相談が実施されます。また、通いの場等でのフレイルチェックシートによりフレイル状態であることが把握された場合にはハイリスクアプローチへつなぐことになります。
仁田まさとしは、高齢者の自立した生活への支援に努めます。
ニッタ マガジン Vol.690 2024.06.17
サイエンスエリートの育成を目指す
このほど、横浜市立横浜サイエンスフロンティア高校(Yokohama Science Frontier High School:以下YSFH)を視察し、サイエンスに特化した特色ある教育について藤本貴也校長らと意見交換しました。
YSFHは、「先端的な科学の知識・智恵・技術・技能を活用して、世界で幅広く活躍する人間の育成」を教育理念として、平成21年4月に開校しました。「サイエンスの力」で予測困難な時代に対応し、新たな時代を切り拓く担い手として「サイエンスエリート」の育成を目指しています。
文部科学省のスーパーサイエンスハイスクール(SSH)に指定され、中でも全国の約10校しかない「SSH科学技術人材育成重点枠」にも指定されています。
例えば、全国SSH生徒研究発表会文部科学大臣賞、化学グランプリ2022大賞、全国物理コンテスト「物理チャレンジ」2022高校生銀賞・附属中生優秀賞、第5回中高生情報学研究コンテスト最優秀賞・文部科学大臣賞など、目を見張る活躍を見せています。
これら教育活動の源流は、「驚きと感動による知の探究」との教育方針にみられます。
また、国際理解教育および外国語教育の水準のさらなる維持向上に向け、継続的発展的に取組む高校などを中心に構成される文部科学省スーパーグローバルハイスクール(SGH)ネットワークにも参画しています。
平成29年4月には附属中学が開校し、令和5年3月に卒業した12期生が、附属中学から6年間を過ごした生徒と高校から3年間を過ごした生徒の両方が在籍する初めての年次となり、96名の生徒が国公立大学に合格しています。
特別科学技術顧問を務める小島謙一横浜市大名誉教授とは、大学との連携プログラム等について意見交換しました。
仁田まさとしは、豊かな高校教育への取組みを進めます。
ニッタ マガジン Vol.689 2024.06.10
こども・子育て基本条例を制定
1月1日の能登半島地震から23週間となりました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
能登半島では、5月31日時点で断水が解消した(内閣府)とのこと。
今後の復興を願います。
6月5日(水)の市会本会議で、議員提案の「横浜市こども・子育て基本条例の制定」が、共産党他を除く賛成多数で可決成立しました。
「こどもは社会の宝であり、未来を担うのは今を生きるこども達である。」と前文は始まり、「こども取り巻く環境はめまぐるしく変わっており、このような状況の下、全てのこどもが」「幸せを実感できる社会を実現するためには」、「愛され保護される存在」であり「その年齢及び発達の程度に応じて、意見を表明し、多様な活動に参画する」「機会が確保されることが重要」としています。
またその経験は、「こどもが、自立心を養い、自ら研鑽に努め、多様性を受け入れ、他者を尊重する心を身に付けながら成長し、公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画するための基礎となる。」
そして、「こどもにとっての最善の利益が考慮され、全てのこどもが伸び伸びと成長し、その個性と能力を十分に発揮できる環境を整えることは、」「こどもを取り巻く社会全体の責務である」と謳っています。
前文の結びには、「こども・子育てに関する施策を総合的に推進するため、この条例を制定する」としています。
本文は、目的、定義、基本理念、こどもの意見の尊重等、市の責務、市民及び事業者の役割、育ち学ぶ施設の関係者の役割、こども計画等の策定、子育て支援、こどもの養育、広報及び啓発、体制の整備、財政上の措置、市会への報告等、主権者教育で構成されています。
仁田まさとしは、こども・子育て支援施策に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.688 2024.06.03
テレビ・プッシュサービスがスタート
1月1日の能登半島地震から22週間となりました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
能登半島では、今なお2,230戸余(5月21日現在:内閣府)が断水中とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
6月1日(土)から横浜市は、テレビの電源を自動で起動し、緊急地震速報等の緊急情報を音声とテレビ画面でお知らせする「よこはまテレビ・プッシュ」補助事業を開始しました。横浜市防災情報EメールやLアラート等と連携し、リアルタイムに情報が配信されますので、視覚的に分かりやすい画面表示と、シンプルな操作性で、誰でも使いやすくなっています。また、緊急地震速報、避難情報や気象警報等の防災情報に加え、電車運行情報やPM2.5情報、休日夜間診療所問合せ先等の生活情報を配信しますので生活の利便性が向上します。
補助対象者は、「横浜市民」であり「災害情報の取得に不安を感じている方」です。初期費用は専用端末費16,500円、設置・設定費12,100円ですが全額を横浜市が補助します。設置開通後の月額550円(税込)が自己負担額となります。
お申し込みは、サービス提供主体のイッツ・コミュニケーション株式会社まで。
(電話:0120-109-199、E-mail:info@itscom.jp)
補助件数が1,000件に達した時点で令和6年度の事業は終了予定です。
また、よこはまテレビ・プッシュの利用にはインターネット環境が必要です。整備されてない場合は、イッツ・コミュニケーション株式会社にご相談ください。
仁田まさとしは、防災情報配信の多重化に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.687 2024.05.27
妊婦健診の追加助成が補正予算案に計上
1月1日の能登半島地震から21週間となりました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
能登半島では、今なお2,200戸余が断水中とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
5月20日に開会した令和6年第2回横浜市会定例会に上程された補正予算案の中で、妊婦・産婦健康診査事業(以下、妊婦健診)のための1億6,860万円が計上されました。
助成対象者として、
①令和6年4月1日以降に妊婦健診を1回以上受診した方
②上記①の健診受診日から支給申請日まで横浜市内に住民登録がある方
のいずれも満たす方に、妊婦一人あたり50.000円を追加助成する事業です。
本市の調査によると市内公的医療機関における14回の健診費用の最大値は124,240円であり、現状の妊婦健診費用補助券交付額である82,700円とは41,540円の差が生じており、差額相当額として50,000円が設定されました。
令和6年10月から申請の受付を開始し、現在開発中の子育て応援サイト・アプリ(仮称)からのオンライン申請を基本とするとのこと。(郵送による申請も可)
ニッタ マガジン Vol.684で報告の通り、公明党と自民党の横浜市議団は山中竹春市長に対して要望書を提出し、妊婦健診の公費負担額の拡充と事務負担の軽減を要望したところです。
また、妊婦健診への公費助成は、公明党の長年にわたる主張が実り平成21年に14回分へと拡充され、平成25年には恒久的制度となった経緯があります。
6月5日の本会議で補正予算が成立すれば、10月からの申請受付を待つことになります。
仁田まさとしは、安心して妊娠・出産できる環境整備に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.686 2024.05.20
出産費用助成金を10月から申請受付
1月1日の能登半島地震から20週間となりました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
能登半島では、今なお3,100戸余(5月8日:内閣府)が断水中とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
早いもので2ヶ月近くが経過する今年度から横浜市では、出産にあたって独自に出産費用を助成することとなります。
現在、公明党が推進した国からの出産育児一時金として50万円が給付されていますが、出産したお子様1人につき最大9万円が助成されます。
この助成金を受け取ることができる方は、①令和6年4月1日以降に出産した方(妊娠85日以上の死産・流産を含みます)、②出産した日から申請日時点まで横浜市内に住民登録がある方、③健康保険に加入されている方の3つの条件をすべて満たすことが必要です。
助成額は、出産したお子様一人につき最大9万円ですが、支給対象の方が加入する健康保険組合から出産育児一時金の付加給付が支給される場合には、9万円からその額を差し引かれて支給されます。
申請の受付が令和6年10月からスタートします。今後リリースされる子育て応援サイト・アプリ(仮称)を利用して手続が可能となります。
ニッタ マガジン Vol.668で報告の通り、公明党市議団は本年1月に山中竹春横浜市長に対して出産費用助成について、市内の公的病院の出産費用にかかる基礎的費用をカバーする金額とし、申請に当たっては市民の負担軽減を考慮すべきと申し入れた経緯があります。
仁田まさとしは、出産環境の充実に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.685 2024.05.13
学校図書館へ新聞配備を
1月1日の能登半島地震から19週間となりました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
能登半島では、今なお3,100戸余が断水中とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
文部科学省は、「学校図書館図書整備等5か年計画」(令和4年度から8年度)を策定し、令和4年1月に公立小中高全てで図書館に新聞を複数紙置くように通知しています。目安部数を小学校は2紙、中学は3紙、高校は5紙とし、地方財政措置が講じられています。
横浜市の令和4年度の状況としては、2紙以上配備している小学校が68校で20.2%、3紙以上配備している中学校が99校で67.3%となっています。
この3月7日に行なわれた横浜市会予算特別委員会の教育委員会関係の質疑で公明党市議団が取り上げ、教育委員会により一括して契約を行い、事務負担の軽減を図りながら図書館への新聞配備を促進し、7年度から取組みを開始すべきと提案しました。
教育長からは、「教育委員会が一括して新聞契約を行なうことは、学校図書館への新聞配備を進める上で、有効な手段の一つと考えます。併せて、学校の事務作業を減らすことに繋がれば、働き方改革の推進にも資することが期待されます。学校図書館に配備する新聞の選定は、各学校の校長が行なうという前提は崩さずに、国の目標達成と事務負担の軽減方法について、他都市の事例等も参考に検討していきます。」との前向きな答弁を得ました。
今後の具体的な仕組みづくりが求められます。
令和4年12月には、公明党市議団の代表も同席し、県内二つの新聞販売組合の皆様が横浜市教育長に要望書を提出た経過があります。
仁田まさとしは、新聞活用による学習環境整備に努めます。
ニッタ マガジン Vol.684 2024.05.06
妊婦健康診査の拡充を
1月1日の能登半島地震から18週間となりました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
能登半島では、今なお4,500戸余が断水中(4月23日現在)とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
このほど、公明党と自民党の横浜市会議員団は、山中竹春市長に対して、妊婦健康診査の公費負担額の拡充を求める要望書を共同で提出しました。
現在、妊婦健康診査にかかる公費負担額は、全国の都道府県の平均額は108,481円であり、本市における公費負担額である82,700円は指定都市の平均額104,305円と比べても大きく下回っています。
また、2024年度予算における出産費用助成事業新設の審議に関連して示された「出産費用だけでなく、産前産後等の経済的支援の充実を図ること。特に妊婦健康診査にかかる費用の負担軽減については速やかに取組むこと。」との意見が附され、予算が成立しました。
これらを踏まえて、次の2項目を要望しました。
1.妊婦健康診査に係る費用の実態を把握したうえで、早期に公費負担額の拡充を図ること。
2.公費負担額の拡充にあたっては、市民の手続き及び医療機関の事務にかかる負担を軽減するよう配慮すること。
山中市長は、「2024年度中のできるだけ早期の実施に向けて、しっかり取組みたい」と見解を示しました。
母子の健康状態を定期的に確認するための妊婦健康審査の公費助成は、2013年度から恒久的制度に変わりました。それまでの補正予算ごとに、期限付きの「妊婦健診支援基金」の延長を繰り返す“財源確保”ではなく、「恒久化して本予算に組み込むべきだ」との公明党の長年にわたる主張が実ったとの経緯があります。
仁田まさとしは、安心して出産できる環境整備に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.683 2024.04.29
コロナ後から制度利用者数が急増
1月1日の能登半島地震から17週間となりました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
能登半島では、今なお4,500戸余が断水中とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
昨年から新型コロナウイルス感染症が5類に移行して間もなく1年が経過しようとしています。人々の移動も制限なくコロナ禍での光景も過去のものとなり、駅や空港、道路での混雑状況が報道されています。
横浜市交通局では、中学生の校外活動を支援するため、市営地下鉄運賃の50%程度を割引する(小児運賃と同額)運賃制度が施行されています。
土休日および長期休業期間(7/21~8/26、12/26~1/6、3/26~4/6)に適用され、学校長が発行した校外活動実施証明書を提示することで、人数要件によらず、また、公立・私立を問わず小児用切符での利用が可能となる制度です。
この制度は、令和2年度の8月から開始され、2年度は235件、乗車人数が延べ2,415人の利用実績でした。年度を通じて利用が始まった令和3年度は756件、乗車人数が7,232人、令和4年度は1,514件、乗車人数が16,221人と倍増しました。
このほど、アフターコロナとなった令和5年度の利用実績が2,471件、利用人数が30,559人と示されました。
ニッタマガジンVol.617でも紹介の通り、この制度の誕生は平成29年秋に頂きました中学校のPTA会長を経験されたTさんからのお声が始まりです。早速実現への取組みを開始し、具体的な検討を経て制度が実現したものです。
仁田まさとしは、中学生の校外活動支援に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.682 2024.04.22
大都市としての行財政制度の充実
1月1日の能登半島地震から16週間となりました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
能登半島では、今なお5,300戸余が断水中とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
先週19日に、この1年間所属した大都市行財政制度特別委員会の最終委員会が開かれ、具体的な取組みである指定都市の「国の施策及び予算に関する提案」と「令和6年度大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望」の結果が報告されました。
「国の施策及び予算に関する提案」は市長・議長から各政党や府省庁に対して、
○感染症や物価高騰への対応に関する提案(4項目)
○財政・大都市制度に関する提案(2項目)
○個別行政分野に関する提案(8項目)
の提案が行なわれました。
それにより感染症や物価高騰への対応、地方交付税の必要額の確保、子ども・子育て支援の充実、脱炭素社会の実現、基幹業務システムの統一・標準化における課題解決、インフラ施設の長寿命か対策及び国土強靱化の推進に関する提案項目に成果が得られました。
また、「令和6年度大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望」は幹事市(神戸市)の市長・議長により総務省や政党、衆参総務委員会へ要望行動が実施されました。さらに、同特別委員会委員により政党へも要望され、公明党へは令和5年11月6日に要望しました。
税制関係の要望は真の分権型社会の実現のための国・地方間の税源配分の是正など5項目、財政関係の要望は国庫補助負担金の改革など4項目です。
これにより、一般財源総額や地方交付税総額が全年度を上回る額が確保されました。
仁田まさとしは、今後も施策の推進と財源の確保に努めます。
ニッタ マガジン Vol.681 2024.04.15
初めての投票状況調査
1月1日の能登半島地震から15週間となりました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
能登半島では、今なお6,200戸余が断水中とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
このほど横浜市の選挙管理委員会事務局は、要介護認定を受けている方及び障がいのある方の投票状況について、要介護度や障がいの等級ごとに投票率の集計結果を発表しました。
令和5年4月9日執行の横浜市議会議員選挙について
①要介護・要支援認定者(以下:介護)
②愛の手帳(療育手帳)所持者(以下:知的)
③身体障害者手帳所持者(以下:身体)
④精神障害者保健福祉手帳所持者(以下:精神)
の283,628人を対象として認定者(手帳所持者)一覧と選挙人名簿を突合して得られたものです。
全有権者の投票率が42.8%に対して、介護は24.3%、知的は27.5%、身体は36.5%、精神は36.7%との結果でした。
それぞれ等級別投票率では、要支援1が46.7%と全有権者より高く、精神3級では42.1%と全有権者と同程度でした。
また、期日前投票の割合は、全投票者の27.9%に対して、介護が30.8%、知的が30.1%、身体が33.8%、精神が34.9%の方が利用されていました。
市選挙管理委員会事務局は、「この集計結果について、専門部署に知見をいただき分析を進め、投票環境向上に向けた具体的な取組みを検討していきます」との考えを示しています。
令和5年10月の決算特別委員会の局別審査における、このような投票状況を調査し投票に行きづらい事情のある方も投票しやすい環境を向上させていくことが必要との提案が、具体的な取組みとして進み始めました。
仁田まさとしは、投票環境の向上に努めます。
ニッタ マガジン Vol.680 2024.04.08
木造住宅の倒壊から命を守る
1月1日の能登半島地震から14週間となりました。
内閣府の発表(4月2日)によれば、この地震によりこれまでに245人の尊い命が失われ、1,300人の皆様が負傷されています。家屋の被害は全壊が8,600棟余、半壊は18,000棟を超えています。また、ライフラインの被害では6,700戸が断水中とのこと。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
一日も早い復旧・復興を願います。
横浜市内の住宅の耐震化率は、令和2年度時点で93%(戸建て住宅88%、共同住宅96%)となっており、令和7年度までに95%(戸建て住宅92%、共同住宅97%)となることを目標としています。そのために、旧耐震基準で建てられた木造の個人住宅や分譲マンションなどを対象に、耐震診断や補助事業などが実施されています。
大地震が発生した際に木造住宅の倒壊を防ぐには耐震改修工事等が最良の防災対策ですが、費用等の課題により難しい場合は、命を守るための減災対策もあります。
それが、比較的安価で設置が簡易であり、建物が倒壊しても最低限の生存空間を確保できる防災ベッド(平均費用:約50万円)や耐震シェルター(平均費用:約170万円)です。
昭和56年5月末以前に建築確認を得て着工された旧耐震基準の木造住宅にお住まいの方向けに、防災ベッドには10万円を上限として、耐震シェルターには30万円を上限として設置費を補助しています。
令和6年度からは、10万円ずつ拡充され、それぞれ補助上限が20万円、40万円に増額されています。
仁田まさとしは、木造住宅倒壊から命を守る取組みに努力します。
ニッタ マガジン Vol.679 2024.04.01
こども家庭センターのモデル実施
1月1日の能登半島地震から13週間となりました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
能登半島では、今なお9千戸余が断水中とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
令和6年度から、「こども家庭センター」が3区(鶴見区、港南区、泉区)でモデル実施されます。
横浜市では、出産から子育てへの切れ目ない支援を行なう「子育て世代包括支援センター」と支援が必要な家庭の早期発見、虐待の未然防止、再発防止等へこども・家庭・妊婦に向けた切れ目のない支援を目指す「こども家庭総合支援拠点」を設置してきており、公明党市議団は全区整備を強力に推進してきました。
「こども家庭センター」は、「子育て世代包括支援センター」や「こども家庭総合支援拠点」の意義や機能を維持した上で組織を見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行なう機能を有する機関として設置されるものです。
これまでの機能に加え、妊娠期から妊産婦支援、子育てや子どもに関する相談を受けて支援をつなぐサポートプランの作成や、多様な家庭環境等への支援体制の充実・強化を図るための地域資源の開拓を担います。
そのために、新たに配置される統括支援員が中心となり、子ども家庭支援員等と保健師等が連携・協力しながら一体的に支援します。
これまで、予算・決算特別委員会で「子育て世代包括支援センター」や「こども家庭総合支援拠点」機能を提案してきており、全区設置が完了する令和4年の予算第一特別委員会の局別審査において、「こども家庭センター」設置に向けた円滑な対応を求めています。
仁田まさとしは、「こども家庭センター」の全区設置を促進します。
ニッタ マガジン Vol.678 2024.03.25
医療局審査で質疑~帯状疱疹ワクチンの定期接種化に向けて
1月1日の能登半島地震から12週間となりました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
能登半島では、今なお1万3千戸余が断水中とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
3月5日(火)に行われた横浜市会予算第一特別委員会の医療局関係の質疑報告として、最後に「帯状疱疹ワクチン」についてお伝えします。
令和4年10月に、公明党横浜市議団は山中竹春市長に対して帯状疱疹ワクチンの早期定期接種化と全額国庫負担を国に働きかけるよう要望して以降、市長が国に粘り強く要望してきたこともあり、昨年11月に国の厚生科学審議会で5年ぶりに議論が再開しました。今後の本格的な議論が期待されます。
帯状疱疹は重症化すると生活の質を著しく低下させ、免疫力が徐々に低下する高齢者の発症リスクが高いことから、予防効果のあるワクチンを求める多数の声が寄せられています。
公明党市議団の要望を受け、市は令和5年度予算に調査費を計上し、国民健康保険のデータをもとに帯状疱疹に関する分析を行ない、例えば発症率は65歳から69歳の区分で1千人に9人との結果等を得ています。
令和6年度には社会保険のデータを分析し、国保データでは把握しきれない働く世代の新規患者数の把握や10年前からの傾向、全年齢層の状況などを分析していく予定です。
これらのデータを基に引き続き国へ強く要望していくことが求められます。
神奈川県内では6市町村が独自の公費助成を実施しており、令和6年度に開始する自治体もあります。横浜市独自の公費助成も検討すべきと強く要望しました。
仁田まさとしは、帯状疱疹ワクチン対策に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.677 2024.03.18
医療局審査で質疑~災害時の透析医療
1月1日の能登半島地震から11週間となりました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
能登半島では、今なお1万5千戸余が断水中とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
今週も、3月5日(火)に行われた横浜市会予算第一特別委員会の医療局関係の質疑内容をお伝えします。
東日本大震災でも大きな課題でしたが、ライフラインが途絶えますと透析医療の継続が困難になります。今回の能登半島地震においても、厚生労働省資料によりますと石川県では、43透析医療機関のうち、最大7機関で透析ができない状態になり、最大360人が日頃っている機関での透析を受けられない状況とのこと。
横浜市では、東日本大震災以降に災害時透析医療体制の検討を行ない、市内の災害拠点病院を中心として11のブロックにグループ化し、透析医療の継続体制が構築されています。
しかし、コロナ禍により各ブロックでの会議が中断され、ブロック内で共有すべき各施設の災害時透析機能維持のための設備状況やかかりつけ患者数などの情報の更新、具体的な災害対策の検討が進んでいません。
災害時透析医療体制の充実に向けた今後の対応を求めたところ医療局長からは、
① ブロック会議を早期に開催し、体制の確認を行なう。
② 市内の111透析医療機関の災害時の患者受入許容数やライフラインの維持機能などの対応力を把握する。
③ 災害状況に応じた具体的連携方向を整理するなど、ブロック単位の対応を確認する。
④ 透析関係団体や神奈川県と広域搬送に係る輸送手段などを具体的に検討する。
との答弁を得ました。
仁田まさとしは、災害時の透析医療の充実に努めます。
ニッタ マガジン Vol.676 2024.03.11
医療局審査で質疑~小児がん対策
東日本大震災から13年が経過しました。また、1月1日の能登半島地震から10週間となりました。犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。公明党県本部は、昨日防災減災キャンペーンを行うなど、震災の風化に抗い「心の復興」「人間の復興」に努めます。
能登半島では、今なお、約1万7千戸が断水中とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
先週3月5日(火)に行われた横浜市会予算第一特別委員会の医療局関係の質疑に立ちました。少し連続して質疑内容をご報告致します。
令和6年度には、小児がん対策が拡充されます。
専門性の高い診療を行なうための小児がん連携病院である県立こども医療センター、横浜市立大学附属病院、横浜市南部病院で、長期のフォローアップを行なっていますが、新たに、小児がん治療後の晩期合併症の予防・治療・支援を行なう地域医療連携体制の構築に向けた検討が行なわれます。
晩期合併症とは、治療を終えた数ヶ月から数年後に、がんそのものからの影響や、薬物療法、放射線治療など、治療の影響によって生じる合併症のことです。
晩期合併症の早期発見には、就学や就職による学校保健安全法や労働安全衛生法に基づく健康診断だけでは、検査項目が不足していることを指摘しました。
医療局長からは、小児がんの治療を受けた方が、成人後に健康管理として受けられる検査の実施に向けて検査項目の検討や実施医療機関の調整を進めるとの前向きな答弁を得ました。
仁田まさとしは、小児がん対策の充実に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.675 2024.03.04
高齢者の社会参加への試み
1月1日の能登半島地震から9週間が経過しました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
今なお、約2万戸が断水中とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
明年2025年は団塊の世代の皆様が後期高齢者となり、2040年には団塊ジュニア世代が65歳以上となり高齢化率35%と予測されています。
医療・介護などによる高齢者を支える仕組みの一方で、増加する高齢者の皆様の社会参加により、活力ある地域を支える担い手として活躍できる仕組みも重要です。
令和6年度には高齢者の社会参加を促進する新たな2つの取組みが進みます。
一つは、「通いの場」などへ参加することでポイントを付与する「社会参加ポイント事業」です。新年度に、スマホアプリの開発とモデル実施が予定されています。
「通いの場」等への参加状況や参加者の健康状態などのデータを収集し,医療、介護、保健データと掛け合わせた多面的な分析が行われ、介護予防施策等へと反映されます。
もう一つは、様々な経験を持つシニアとホランティア活動を結ぶ「シニア×生きがいマッチング事業」です。コー-ディネーターが、希望者の経験やスキルを聞き取り、経験等に応じた活動の有無を地域活動団体や企業等に確認し、希望者と活動をマッチングさせます。高齢者の生きがいづくりにより健康寿命の延伸にもつながり、地域活性化が期待されます。
本年度に一部モデル実施が始まっており、令和6年度にはさらに地域が拡大される予定です。
仁田まさとしは、高齢者の「自分らしい暮らし」を支えます。
ニッタ マガジン Vol.674 2024.02.26
福祉のまちづくりへの一歩
1月1日の能登半島地震から8週間が経過しました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
今なお、約2万2,000戸が断水中とのこと。一日も早い復旧・復興を願います。
先週、横浜市会においては本会議が開かれ、各会派代表による予算代表質疑と予算関連質疑が行われました。本日より予算特別委員会で局別に詳細な質疑が行われます。
今週のニッタマガジンでは、新年度予算案の中から主張が反映された“福祉のまちづくり”や“障がい児者への支援”についてご報告します。
まず、「パーキングパーミット制度」の導入です。
車椅子使用者用駐車施設は、公明党が推進したバリアフリー法のもと設置が促進されてきましたが、そのスペースに障がいのない人が駐車するなどの課題もあります。一方で、妊婦さんや人工透析などの内部障がいで歩行が困難なものの、外見からは障がいと分からない方も多く、このような方たちが利用対象者であることを明確にする利用証を交付する制度が「パーキングパーミット制度」です。
市は、新年度の7月頃導入予定とのことです。
令和5年3月の健康福祉・医療委員会で導入を強く主張した経緯があります。
また、障がい児・者の日常生活で必要な移動や動作等を補完・代替する補装具費の支給について、国が新年度予算において「障がい児」について所得制限を撤廃することとなり、この動きを踏まえて、横浜市は所得制限により制度の対象とならなかった「障がい者」の給付対象者を拡大します。
令和5年5月に、公明党市議団は山中竹春横浜市長に、「障がい児・者への日常生活用具及び補装具を支給するための支援の拡充」を国へ求めるよう要望していました。
仁田まさとしは、市民に寄り添う施策の実現に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.673 2024.02.19
防災・減災への備え
1月1日の能登半島地震から7週間が経過しました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
今なお、約2万9,500戸が断水中とのこと。
一日も早い復旧・復興を願います。
横浜市においても、より一層進めなければならない防災・減災対策について、令和6年度予算案に公明党の主張も大きく反映された事業の一部をご報告致します。
初めに、情報伝達手段の強化です。
緊急地震速報などの災害情報が即時・確実に届き、すぐに避難行動をとることができるよう、テレビを自動起動させ、プッシュ通知によって災害情報をお知らせする「テレビプッシュ事業」が予算計上されました。
利用対象となる方は、横浜市民でスマホをお持ちでない方や災害情報の取得に不安を感じていらっしゃる方で、1,000世帯を予定しています。
端末費用(16,500円)と設置・設定のための費用(12,100円)の全額が補助され、利用者は月額550円の利用料を負担することになります。
また、インターネット環境がない方は、地域BWAの回線契約が可能です。この地域BWA(地域広帯域移動無線アクセスシステム)は、大きな携帯会社の使用している周波数のすき間の電波を利用する電気通信業務用の無線システムです。
4月から広報が行われ、6月より募集開始予定です。
地域防災拠点等の備蓄品も充実します。
寒さ対策の充実のためアルミブランケットが全量一斉更新され、応急対策に活用されるブルーシートが追加配備されますが、これまで折々に主張してきた液体ミルクが新たに備蓄されます。また、粉ミルクの調乳などに活用できるカセットコンロ等も追加配備されます。
仁田まさとしは、防災・減災への取組に努力します。
ニッタ マガジン Vol.672 2024.02.12
「こども未来戦略」と横浜市予算案
1月1日の能登半島地震から6週間が経過しました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
今なお、避難者が1万3,500人を超え、約3万7,500戸が断水中とのこと。
一日も早い復旧・復興を願います。
今週は、新年予算案で要望が具体化した子育て支援策の一部をご報告致します。
公明党の「子育て応援トータルプラン」の多くが反映された政府のこども未来戦略「加速化プラン」が国の新年度予算のポイントの一つです。3カ年で進めますが、実現すれば、OECDでトップクラスのスウェーデンを超える子育て支援策となります。
児童手当は、令和6年10月分から所得制限が撤廃され高校生年代まで支給されます。支払い月がこれまでの年3回から年6回(偶数月)となり、拡充後は令和6年12月支給が初回となります。
横浜市予算案にも、そのために557億円3千万余円が計上されました。
出産育児一時金は、公明党の推進により平成6年度から30万円、平成21年度には42万円、令和5年度から50万円と段階的に引き上げられました。
横浜市では「賄いきれない」との声が公明党市議団にも寄せられ、1月5日に、山中横浜市長に「出産費用の負担軽減に関する要望書」を提出しました。
その結果、横浜市予算案では、9万円(上限)を補助する横浜市独自の「出産費用助成事業」として20億5千万余円が計上されました。
出産・子育て応援交付金は、令和4年度から妊娠届出時に5万円(相当)、出生届出時に5万円(相当)支給されていますが、令和7年度から制度化されることとなります。
横浜市では、伴走型相談支援とそれぞれ5万円相当のギフト支給する「出産・子育て応援事業」として27億7千万余円が計上されました。
仁田まさとしは、子育て支援の拡充に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.671 2024.02.05
学校のエアコン設置が進みます
1月1日の能登半島地震から5週間が経過しました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
連日、災害ボランティアの皆様の活動や飲食店の再開、仮設住宅の模様などが報道されていますが、一方で、水道が断たれている地域が未だ4万戸余とのこと。
一日も早い復旧・復興を願います。
先週は、1月29日に示されました令和6年度横浜市予算案について、局別に説明を受ける研究会が終日行われました。これから数週間にわたって、事業内容についてご報告いたします。
市立学校の施設環境の確保として、空調設備は教育環境向上に大変有意義な事業です。
公明党横浜市会議員団が強く要望した空調設備の設置が進みます。
体育館は、児童生徒の体育の授業、部活動や行事のためだけでなく、災害時の避難所にも活用される公益性のある施設であり、近年の猛暑は熱中症などの二次被害をもたらし課題となっています。
令和6年度は体育館にエアコンを27校、大型冷風機を10校に新設の予定です。
また、校内調理による給食を提供するための給食調理室は、大型の調理釜などもあり、猛暑の中では調理員の皆様の健康も大変心配されます。
令和5年度には空調設備の設置に向けて様々な調査が行われ、その結果を基に令和6年度に9校の給食調理室に試行設置され、効果を検証することになります。
さらに、学校の職員室等の設置年数が古い既存空調の計画的な整備も進めており令和6年度は66校の改修工事が行われます。
仁田まさとしは、学校の空調設備の充実に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.670 2024.01.29
特別市の法制化に向けて
1月1日の能登半島地震から4週間が経過しました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
報道によりますと、ボランティアの皆様の活動が始まりましたが、今なおライフラインが確保されていない地域もあります。一日も早い復旧を願います。
先週23日と25日に、副委員長を務める横浜市会大都市制度行財政制度特別委員会(伊波俊之助委員長)が、松本剛明総務大臣、古屋範子衆院総務委員会、新妻秀規参院総務委員長に、「特別市の法制化に関する要望」を提出しました。
要望内容は、次の3項目です。
1.特別市の法制化の早期実現
2.内閣総理大臣の諮問機関である地方制度調査会における大都市制度改革論議の推進
3.地方分権改革の推進
ニッタマガジン VOL.640でも記しましたが、「横浜市が実現を目指す新たな大都市制度である特別市とは、原則として国が担うべき事務を除くすべての地方の事務を横浜市が一元的に担い、その仕事量に応じた税財源も併せ持つ制度です。」また、「特別自治市となることで、これまでの、子育て支援、医療政策、崖地の安全対策、都市計画、就業支援・雇用対策などの二重行政が解消されサービス向上が期待されます。」
要望の場においては、様々な意見交換を致しましたが、松本大臣からは「横浜市会としての特別市の法制化の要望をしっかりと受け止めさせていただく。」と、古屋委員長からは「特別市制度については、地方分権を目指す大きな目標として理解した。」と、新妻委員長からは、「参議院総務委員会でも委員がこのようなテーマを積極的に取り上げてもらえるよう考えたい。」とのコメントがありました。
仁田まさとしは、特別市への機運醸成に努めます。
ニッタ マガジン Vol.669 2024.01.22
市立高校の特色を探る
1月1日の能登半島地震から3週間が経過しました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
依然として能登地方を中心に活発な地震活動が続いているとのことです。政府は19日に「非常災害」に指定する政令を決定し、インフラの復旧工事を国が代行できるようになりました。一日も早い復旧を願います。
このほど、横浜市立桜丘高校(星野校長)を訪問し、教育概要を聴取しながら特色ある教育等について意見交換しました。
同校は昭和2年5月31日に横浜市立実科高等女学校として開校。令和9年(2027年)には100周年を迎える歴史を持ちます。
同校は、市教育委員会から進学指導重点校に指定されており、教育課程の特徴は、文系理系に偏らず「3年間を通してバランスよく学べる科目構成」、一人ひとりの学習の伸びを支える「基礎力重視」と、その結果としての「進路実現支援」としています。具体的には、「一人ひとりによりそったキャリア教育-計画的・組織的な進路指導」として、進路教育相談の実施など13の取組が行われており、ほぼ100%の生徒が進学を希望している状況とのこと。
県内でも特色あるキャリア教育の一環として、「教員養成講座~桜ACEプログラム」が本年度から開設されています。3年間の様々な体験や活動を通して教職に対する探究力を育み、自己の資質・能力の向上を目指し、1年次は「教育を知る」、2年次は「体験する」、3年次は「進路実現」に向けた教員養成講座を履修できます。
この課程を経た1年生は、7年後に教員試験を受験することとなりますが、その継続に期待が膨らみます。
仁田まさとしは、市立高等学校の充実に努めます。
ニッタ マガジン Vol.668 2024.01.15
出産費用で申し入れ
1月1日の能登半島地震から2週間が経過しました。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
公明党「令和6年能登半島地震災害対策本部」は12日、林芳正官房長官に対し、国会議員と地方議員で連携して実施した被災地の現地調査を踏まえた緊急要望を行ったところです。引き続き被災地支援に取り組みます。
公明党横浜市会議員団は5日、山中竹春横浜市長に対して、出産費用の本市独自支援策について要望書を提出し下記の4項目を申し入れました。
1.令和6年度予算において、出産費用について世帯の所得に関わらず助成するなどの経済的負担の軽減施策を実施すること。
2.その軽減施策については、市内の公的病院の出産費用にかかる基礎的費用を100%カバーするような制度とすること。
3.助成制度の検討にあたっては、市民の申請の負担を軽減するとともに、速やかな支給が可能となるよう、一律の助成額とすること。
4.国に対し、出産費用における保険適用の検討にあたり、自己負担額は全額国費で賄うとともに、公費負担については、国による財政負担を前提に進めることを引き続き要望すること。
横浜市による出産費用調査では、市内分娩取扱い施設の基礎的費用の平均値は548,224円、中央値は555,000円であり、本市では国の出産育児一時金を充当しても費用負担が発生している状況であることと、84.5%のご家庭が経済的負担を感じていることも明らかとなりました。
子どもさんを望まれる全てのご家庭が躊躇なく、安心して子どもを産み育てられる環境を作るべく、公明党市会議員団は実情に合わせた費用助成とするよう重ねて要望してきました。
仁田まさとしは、安心して子どもを産み育てられる横浜の実現に取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.667 2024.01.08
能登半島地震への被災地支援
本日は成人の日。新成人の今後のご活躍をお祈り申しあげます。
1月1日16時10分ごろ、石川県能登半島を震源とするマグニチュード7.6の地震が発生し、多数の犠牲者と甚大な被害が発生しています。
犠牲になられた方々のご冥福をお祈りし、被災された皆様にお見舞い申しあげます。
横浜市は2日、「横浜市被災地支援チーム」を発足しました。
水道局が、3日から富山県氷見市に8人の職員と4t給水車2台を派遣。また、石川県小松空港に航空消防隊1隊(8人)と消防ヘリ「はまちどり2号機」が出動。さらに、石川県珠洲市役所に向け3日に職員6人と物資輸送車(救援物資:水缶、ビスケット、ブルーシート、毛布、生理用品、子供用おむつ、高齢者用おむつ、トイレパック)1台と災害対策車を派遣しました。
5日には石川県羽昨郡志賀町へ応急対策職員として20人の派遣を決定。また、5日から石川県内の水道施設復旧に向けた調整のため、水道局より4人の職員(土木職員)が派遣されています。
6日から保健師2名と業務調整員2名(10日からは保健師2名と業務調整員1名)が派遣され、避難所での健康支援業務や在宅要支援者の健康管理業務にあたります。
富山県氷見市への応急給水隊の活動に目途がついたことから7日から石川県に移動して応急給水活動を継続しています。また、7日から水道施設復旧のため第二次応急復旧隊として石川県に4人の職員が派遣されました。
この間、5日には体制強化のため、「横浜市被災地支援チーム」から「横浜市災害応援対策本部」に移行しています。
公明党横浜市議団は、5日に山中竹春横浜市長に要望書を提出した際に、全力支援を要望しました。
仁田まさとしは、さらに災害対策に努力します。
ニッタ マガジン Vol.666 2024.01.01
結党60年と2024年
新たな年を迎えました。
本年も、ニッタマガジンを宜しくお願い申しあげます。
1964年11月17日、公明党が結党され、今年は60年目を迎える年となります。
公明党の不変の原点は、結党の2年前に開催された公明政治連盟(公政連)第一回全国大会での党創立者池田大作創価学会会長(当時)の次の挨拶(要約)にあります。
第一は、「生涯、永久に、公政連は団結第一でいっていただきたい」「派閥や、反目のあるようなことが、もしも、毛筋でもあったならば、即座にわが政治連盟は(中略)解散すべきである」。
第二は、「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆のために戦い、大衆の中に入りきって、大衆の中に死んでいく」。
第三は、「政治の面の勉強、あらゆる知識の吸収、(中略)さまざまな勉強をしきっていただきたい」。
この原点を、あらためて心肝に染めて参ります。
2024年の十干十二支は、甲辰(きのえ・たつ)。
甲は十干の第一番目、生命が誕生した状態と言われます。
辰は、十二支の中で唯一実在しない龍を意味し大自然の躍動を象徴、また十二支の5番目で草木の成長が一段落して整った状態を表すとも言われています。
合わせますと、「成功という芽が生長していき、姿を整えていく」「春の日差しが、あまねく成長を助く年」との記載が報道に見られます。
2024年の1月には新NISAが始まり、台湾総統選挙、3月にはロシア大統領選挙、4月からは「2024年問題」として労働時間外上限規制の猶予がなくなり、6月には所得税減税、8月にパリ五輪開催、9月には自民党総裁任期、11月に米大統領選挙などが予定されます。ウクライナや中東情勢も注目されます。
仁田まさとしは、「市民のために」心新たに始動します。
ニッタ マガジン Vol.665 2023.12.25
横浜10大ニュースと港ビッグニュース
今年も一週間を残すのみとなりました。
年末恒例となりました「横浜10大ニュース」が10,617人市民の投票で決定しましたので、一部をあらためてご紹介します。
第1位は、相鉄・東急直通線の開業です。
相模鉄道と東急電鉄が相互乗り入れして直通運転が3月に始まりました。横浜市西部や県央部と東京都心部が直結し交通利便性が飛躍的に向上することが期待されます。
第2位は、慶応義塾高校が夏の甲子園優勝です。
第105回全国高等学校野球選手権記念大会で、仙台育英高校に決勝で勝利し、107年ぶり2度目の優勝を果たしました。「エンジョイベースボール」とのスローガンが話題となりました。
第3位は、Kアリーナの開業です。
2万人を収容できる世界最大級の音楽特化型アリーナが9月、みなとみらい21地区に開業しました。横浜生まれの2人組アーティスト“ゆず”によるこけら落とし公演で始動となりました。
その他、新型コロナウイルス感染症の5類への移行が第4位、小児医療費の小学校3年までの無料化が第5位、関東大震災から100年の経過が第9位となりました。
また、横浜港に関連する「ビッグニュース」として、国際クルーズが本格的に再開し日本で初めて5隻同時着岸が見られ、新たなクルーズ船「飛鳥Ⅲ」の船籍が横浜港に決定しました。さらには、本牧ふ頭に超大型LNG燃料コンテナ船が入港し、A突堤に全国を先駆ける「陸上電力供給設備」の整備に着手するなど、脱炭素施策の進展があげられます。
仁田まさとしは、明年もさらなる横浜の発展に努めます。
ニッタ マガジン Vol.664 2023.12.18
支援額を上回る税収の効果
過日開催された横浜市会の国際・経済・港湾委員会において、市内への企業立地に関する報告がありましたのでご紹介します。
横浜市内への企業立地を促進し、市民・市内雇用を増やし、企業の事業機会の拡大を図ることで、市内経済の活性化に寄与することを目的として、平成16年4月に「横浜市企業立地等促進特定地域などにおける支援措置に関する条例」(以下企業立地促進条例)が制定されました。
この条例は、一定の条件を満たす事業計画を実施する者を認定し、助成金の交付及び法人市民税の軽減等を行うものです。これまで6期にわたり改正が行われ、本市経済発展に大きな役割を果たしてきました。
これまでの認定の実績として令和5年11月末現在、170件の企業立地を認定し、本社・研究所の新規進出や事業拡張に伴う再投資などを促してきました。
認定企業立地前と比較すると、約4万4千人の雇用が増え、市内・準市内企業に対し、建設・設備投資は累計で約6,054億円(令和4年12月現在)、事業活動は年間で約802億円(同)に発注が生み出されています。
特に注目は令和4年度までの実績で、累計の税収は約777億円、支援額は約472億円となっており、税収が約305億円上回っていることです。
現在の条例は令和5年度末をもって適用期間の期限を迎えます。企業立地を取り巻く環境の変化やまちづくりの動き、企業ニーズなどを踏まえた改定を検討し、令和6年第1回市会定例会に改正案を提出する予定とのことです。
委員会質疑においては、国内外からの良好なアクセスや多くの技術者・研究者・理工系大学を有する横浜市の強みに加え、今後とも暮らしやすい居住空間の提供などが必要と主張しました。
仁田まさとしは、さらなる企業誘致の促進に努力します。
ニッタ マガジン Vol.663 2023.12.11
県でも緊急要望と補正予算
公明党神奈川県議団は11月24日(金)に、黒岩祐治県知事に対して「物価高騰から県民を守るための緊急要望」を行いました。
今般、政府が決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として予算が追加された「重点支援地方交付金」を活用しながら、物価高騰から県民・市民の生活を守り、経済の着実な回復を図るための具体的な取組として、
○LPガスを利用している県民・企業の負担軽減策を講じること
○福祉施設や医療機関、私立学校などに対する光熱費高騰対策
○中小貨物輸送事業者への燃料価格高騰に関連する支援
○県立特別支援学校の学校給食への支援
○飼料・肥料の購入費補助など農林水産業への支援
○一般公衆浴場の燃料費・電気代の負担増への支援
を、提言しました。
12月6日(水)に神奈川県より補正予算案が示されましたので、主な内容をご報告いたします。
LPガス料金の高騰対策として販売事業者へ支援金を支給します。
また、病院・診療所などの医療機関、高齢者・障がい者などの福祉施設、私立学校、生活者困窮者支援団体などへ電気代・ガス代等の高騰による負担を軽減するための支援金を支給します。さらには、一般公衆浴場の燃料費及び電気代の負担増への補助、農林水産業者への支援として、と畜場の光熱費、きのこ生産者の燃料費、漁業協同組合等の電気代の高騰分を補助します。
中小企業者等への支援として特別高圧受電業者の負担軽減、資金繰りのための信用保証料補助が行われます。また、「物流の2024年問題」への対応として運輸事業者への支援が行われます。
県議会常任委員会での議論を経て、18日の本会議での採決が予定されています。
仁田まさとしは、県・市連携して物価高騰対策と経済再生に取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.662 2023.12.04
緊急要望と補正予算
公明党横浜市会議員団は11月21日(火)に、山中竹春横浜市長に対して「物価高騰対策と経済再生に向けた緊急要望」を行いました。要望の要旨をご報告します。
昨年来からの物価高騰は、いまだ市民生活や事業活動に深刻な影響を与えています。経済再生に向けては、物価高騰対策に加え、中小企業が持続的に賃上げできるような支援を行う必要があります。
政府の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」には、所得税の定額減税や低所得世帯への給付金に加え、各地域の実情に合わせて、きめ細やかな支援策を進めることができる「重点支援地方交付金」の予算が追加されました。
横浜市におきましても、「重点支援地方交付金」を効果的に活用し、物価高騰から市民生活を守り、経済の着実な回復を図るため、具体的な取組を要望したところです。
11月30日(木)に開会した横浜市会第4回定例会で発送され、12月7日(木)に提出される議案の中で、次のような補正予算案(抜粋)が示されました。
国の総合経済対策を踏まえ、特に影響が大きい住民税非課税世帯に対する給付金7万円を、令和6年3月から順次給付する予定です。
また、物価高騰対策と脱炭素ライフスタイルへの行動変容にもつながる省エネ家電の購入支援として、エコハマ(横浜市エコ家電応援キャンペーン第2弾)が実施予定です。一定の省エネ基準を満たすエアコン、冷蔵庫、LED照明器具について購入金額の20%還元が、令和6年6月中に開始予定です。
その他、中小企業ものづくり成長力強化事業や商店街支援、自治会町内会会館脱炭素化推進事業なども予定されています。
今週7日に議案関連質疑が行われます。
仁田まさとしは、物価高騰対策と経済再生に取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.661 2023.11.27
南区制80周年を前に
まもなく巡り来る12月1日(金)に南区が区制80周年を迎え、記念式典および祝賀会が開催されます。昨年、実行委員会が設立され、80周年を広くPRするためののぼり旗やポスター、記念のオリジナルTシャツなどが制作され、「南区制80周年記念」と冠した様々な事業が行われてきたところです。
昭和18年(1943年)12月、中区から分区され南区が誕生。人口は14万5千人余でした。庁舎は南太田一丁目の第一隣保館を改修して使用されていました。
接収を解除された花之木町において昭和33年(1958年)に二代目の区庁舎が建てられました。
三代目の区庁舎は、消防棟、公会堂棟を併設した総合庁舎として昭和49年(1974年)に建てられました。当時は市の公共施設で初めてとなるワンタッチ開放の排煙専用窓が各階に設置され、地下には12.5トンの防火専用水槽が整備されるなど防災設備に特徴を持っていました。跡地は商業施設、デイサービス、子育て支援施設、地域交流施設などの複合施設となっています。
四代目となる現在の区総合庁舎は、平成28年(2018年)2月に共用開始。東日本大震災の経験をふまえ、災害に強く、省エネで環境に配慮された様々な取組が施された庁舎となっています。
80年の間、横浜大空襲で区内40%の被災、大岡川氾濫との闘い、市民の足として活躍した路面電車の昭和47年(1972年)の廃止と市営地下鉄1号線の同年の開通、平成の時代に入って地域ケアプラザ、地区センター、コミュニティハウス、高齢者、子育て支援施設の整備、平成13年(2001年)に区の花「さくら」の制定等など、様々な変遷をたどり、現在に至っています。
仁田まさとしは、あたたかな、より一層住みよい南区を目指します。
ニッタ マガジン Vol.660 2023.11.20
医療的ケア児への支援で意見交換
このほど、神奈川県立こども医療センターを訪問し、新生児科、地域連携・家族支援局局長の星野陸夫先生と、面談する機会を得ました。
星野先生は、1992年にこども医療センターが総合周産期センターを設置するときに入所され、慢性の病気や障がいのある子どもたちを中心に診療が行われているこども医療センターの新生児科に勤務されています。
今回の面談の目的の一つは、令和3年に制定された「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(以下「医療的ケア児支援法」)に基づき進められている施策について、永年にわたりたくさんの命と向き合ってこられた星野先生と現状と課題について意見交換することでした。
とても示唆に富む、有意義な時間となりました。
「医療的ケア児支援法」は、「医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資し、もって安心して子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的と」しています。「医療的ケア」とは、人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいい、「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童としています。
また、公明党の主張で政府の「こども未来戦略方針」に「医療的ケア児などの光のあたらない人々への支援が含まれ」ました。
横浜市では、保育所・学校・放課後児童健全育成事業所等における医療的ケア児の受入れ環境の整備を進め、地域生活を支えるため、医療・福祉・教育等の多分野にわたる相談・調整を行うコーディネーターによる支援が行われています。
仁田まさとしは、医療的ケア児とその家族への支援に取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.659 2023.11.13
民間との連携で楽しみな事業が
横浜市と民間の事業者がコラボレーションする、最近の2題をお知らせします。
11月1日(水)から山崎製パン株式会社横浜第二工場が、横浜市とゆかりの深いドイツにちなんだ商品を開発し、「ランチパック(ドイツ風ビーフシチューと粒マスタード入りポテトサラダ)」の販売を始めました。
ドイツの家庭料理であるグラーシュ(ドイツ風ビーフシチュウ)をイメージしたフィリングをサンドしたものと、マスタードやピクルスを入れたポテトサラダをサンドした2種類のアソートランチパックです。パッケージには、フランクフルト市で運行している、横浜市とフランクフルト市のラッピング電車の写真も掲載しています。
山崎製パン製品お取扱い店で年末(予定)まで販売されています。
横浜市は、平成23(2011)年に同市とパートナー都市協定を結び、山崎製パン株式会社横浜第二工場ではこれまで、横浜市の魅力をアピールする横浜にちなんだ商品を企画開発しています。
株式会社良品計画は横浜市と包括連携協定を締結し、“感じ良い暮らしと社会”の実現を目指して、ニッタマガジンVol.655でも紹介した「横浜マイスター」と連携した取組を行っています。
その一環として、11月17日(金)~12月24日(日)に「無印良品 港南台バーズ」(株式会社良品計画 横浜事業部)において、横浜マイスターである稲見行雄氏が制作した鉄道模型(Oゲージ・C62蒸気機関車)を、手作りキット「ヘクセンハウス」を使った「お菓子の街」とともに展示するほか、11月19日(日)14時~16時、12月24日(日)14時~16時の2日間の実走イベントも実施されます。
どちらもお楽しみいただける企画かと思います。
仁田まさとしは、民間とのコラボ事業を推進します。
ニッタ マガジン Vol.658 2023.11.06
納税手続のデジタル化で利便性を向上
今週は、横浜市会決算特別委員会報告の第3週目。財政局関係の質疑をお伝えします。
横浜市では、税務手続のデジタル化による利便性向上の取組が進められています。
これまで、事業者を対象に平成17年度から法人市民税等の申告のデジタル化を開始し、平成25年度にペイジー納付を導入し、現在では地方税共通納税システム、スマホ決済、クレジット納付にも対応しています。
税務には、申告と納付があります。
電子申告の令和4年の利用率を尋ねると、全税目の合計が政令市で最も高い74.7%となっていました。
一方で、電子納税の令和4年の利用率を尋ねると、個人向けの税目で17.2%、法人向けは12%と大きな差が明らかとなりました。
税務手続について利便性をさらに向上させるため、継続してデジタル化を推進する必要がありますが、今後実施を予定している税務手続を伺うと、新たな3つの手続のデジタル化を予定しているとの答弁がありました。
①令和7年1月から、住民税の電子申告が始まります。
②令和6年度分から、住民税の納税通知書に印字されたQRコードによる電子納税が始まります。
③令和6年度から、会社員向けに現在は紙で配られている個人住民税の特別徴収税額通知書の電子化が始まります。
これらのデジタル化を進めるには、いかに市民の皆様に利便性を実感していただき、利用が進んでいくのかが大切と考え、利用率向上に向けた取組について伺いました。
局長は、「電子申告については国税と連携を深めた広報を進め、電子納税については利便性や利用方法の周知を国や県、税務関係団体や金融機関等と連携して進めて」利用率の向上を図ると答弁しました。
仁田まさとしは、税務手続のデジタル化を丁寧に推進します。
ニッタ マガジン Vol.657 2023.10.30
模擬投票と共通投票所を
今週も、横浜市会決算特別委員会での選挙管理委員会関係の質疑のご報告です。
横浜市議会議員選挙における投票率は、平成15年の49.5%以降、低下傾向を示しており令和5年も42.83%と低投票率が続いています。中でも、10代から20代のそれは26.42%と約16ポイント下回っているように、若年層の低投票率が課題となっています。
現在、教育委員会と選挙管理委員会が平成28年に締結した「主権者教育の推進に向けた協定」に基づき、中学3年生向けの社会科副教材「あと3年」の配布や高校生向けの主権者動画の活用等により主権者教育が行われていますが、県立高校では参院選挙の際に、実際の選挙公報等を用いて、実際の候補者に模擬的に投票する模擬選挙を実施しています。市でも平成28年に実施していますが以降は行われていないことから、模擬選挙などの参加実践型の学習を実施すべきと主張しました。
局長からは、「模擬選挙を含めたよりよい参加実践型の主権者教育の推進に向けて検討」するとの答弁を得ました。
最後に、投票所への利便性向上の取組を取り上げました。
この4月の統一選挙後に有権者の方から、「投票所へ行くには山坂が多くて大変なので、行きやすい隣の投票区の投票所で投票できないか」とのご意見を伺いました。
近年の公職選挙法改正により、選挙区内であれば決められた投票所以外でも投票できる「共通投票所制度」が創設されており、導入により投票利便性は格段に向上します。
実施の考えを質問し、局長からは、「ネットワークシステムの構築など、共通投票所の導入を想定した課題解決に向けて検討」していく旨の答弁がありました。
仁田まさとしは、投票率向上への取組みを推進します。
ニッタ マガジン Vol.656 2023.10.23
障がい者等の投票状況を調査へ
横浜市の令和4年度決算を審査する特別委員会が9月21日に設置され10月18日まで行われました。
10月16日に開かれました選挙管理委員会関係と財政局関係の質疑に立ちましたので3週にわたってご報告します。
今週は21年ぶりの質疑となった選挙管理委員会関係です。
まず、障がいのある方等の投票環境の向上についてです。
東京都狛江市では、この4月の統一地方選挙の際、障がい者手帳を持つ方の投票実態を調査し分析をしています。過日、狛江市役所を訪問し、調査結果を聴取するとともに、意見交換してきました。狛江市の結果では、身体、知的、精神の3障がい者手帳を所持する方の投票率は46.9%と、狛江市全体の50.7%より3.8ポイント低い状況でした。また、色々な仮説とクロス集計などで分析を行っていました。
報道によると、障がい者の投票支援に詳しい京都産業大学の堀川諭准教授は、「これまで障がい者の投票実態は把握されてきておらず、その第一歩になったという点で意義の大きな調査だ」と評価しています。とても示唆に富む取組でした。
質疑の中で、横浜市も障がい者の投票状況を調査すべきであり、その際にはあわせて介護認定を受けている方の投票状況も把握し、投票に行きづらい事情のある方も投票しやすい環境を向上させていくことが必要であると主張しました。
選挙管理委員会事務局長からは、「狛江市の調査結果を確認、分析した上で、投票における対応や障がいの程度に応じたきめ細やかな配慮事項などに活用できる調査の実施について検討してまいります。」との前向きな答弁を得ました。
調査が実施され結果がでましたら、分析と議論をしっかり行いたいと考えます。
仁田まさとしは、誰もが投票しやすい環境づくりに取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.655 2023.10.16
「匠の技」の継承・発展を
先週、横浜市は「第26回横浜マイスターまつり」を11月11日(土)、12日(日)の両日に開催することを発表しました。横浜市技能文化会館(中区万代町2-4-7)を会場として横浜マイスターによる、実演、作品展示、販売及び技能体験教室が行われます。
技能体験教室は有料で12日のみに行われ、ガラスコラージュ体験、名刺入れ作り体験、木下透の剪定講座ライブ、組子のコースター作り体験があり、事前申し込みが必要です。
横浜マイスターという事業は、市民の生活・文化に寄与する優れた技能職者を“横浜マイスター”に選定し、横浜マイスターによる後継者育成、技能・技術の継承及び普及活動を通じて、技能職の振興を図ることを目的と知る事業です。選定に当たっては過去の功績だけでなく、将来の活動への期待も考慮されます。
平成8年度から実施されている事業で、令和5年度も、鉄道模型制作と美容師の2名が選定されるなど、これまでに70名が選定されています。また、横浜マイスターが第一線を退かれたとき、または、ご逝去されたときは、今までのご活躍に敬意を表して、名誉横浜マイスターとなります。
この事業が始まったときは、横浜市の市民局が所管し、伝統芸能としての形を保全する趣旨が強く、その後経済局に移管され、ものづくり、産業の継承・発展のため横浜マイスターをいかに育成・支援していくかとの観点で進められて来ています。
平成20年3月の常任委員会でも、横浜マイスターへの支援拡大を取り上げるなど、折々に議論してきました。
仁田まさとしは、優れた技能、「匠の技」の継承・発展に努力します。
ニッタ マガジン Vol.654 2023.10.09
公園内の受動喫煙対策
今週末の10月14日(土)から11月19日(日)まで、市内の5つの公園を禁煙として受動喫煙対策が試行されます。
具体的には、横浜を代表する観光公園として山下公園と港の見える丘公園、子どもの利用が多い大型遊具がある公園としてこども自然公園、駅に近く喫煙に対してご意見をいただいている公園として藤が丘駅前公園と天王町駅前公園で、公園全体を禁煙とし、ポスターや看板の掲示などにより試行中であることを周知し、現地でアンケート調査を実施することになります。
先に開催された市会常任委員会で、その受動喫煙対策の試行実施内容とともに、この7月から8月にかけて実施された公園での喫煙に関するアンケート調査の実施結果が示されました。
アンケートは、ヨコハマeアンケート、公園を利用する子育て世代を対象とした子育て支援拠点でのアンケート、公園愛護会を対象としたアンケートの3種類で実施されました。
「公園を利用している際に喫煙で迷惑と感じたことがあるか」との問いについては、「よくある」「たまにある」を選択した人がeアンケートでは約6割、子育て世代では約8割、公園愛護会では約5割となっています。
「公園内での喫煙について、どのようなことが迷惑と感じたか」の問いについては、eアンケートと子育て世代では「たばこの煙やにおい」と「吸い殻のポイ捨て」が、公園愛護会では「吸い殻のポイ捨て」が、特に多く選択されています。
公明党横浜市議団はこれまでも、屋外の受動喫煙対策について質疑を通して要望してきています。
仁田まさとしは、公園や歩道での受動喫煙防止に努めます。
ニッタ マガジン Vol.653 2023.10.02
温室効果ガスを有効利用
このほど、公明党横浜市会議員団は横浜市資源循環局鶴見工場(以下鶴見工場)を訪問し、三菱重工グループ・東京ガスと横浜市が連携して、鶴見工場の排ガスからCO2を分離・回収し、水素(H2)と合成してメタンガス(e-Methane:e-メタン)を生成する実証実験であるCCU(Carbon dioxide Capture and Utilization:二酸化炭素の分離・回収、利用)共同実証を視察しました。
水素(H2)と二酸化炭素(CO2)からメタン(CH4)を合成する技術はメタネーションと呼ばれます。再生可能エネルギー等から生成された水素と合成して天然ガスの主成分であるメタンを合成するメタネーションは、政府も「カーボンリサイクル(CO2の再利用)」の有望な技術として位置付けています。
このCCU共同実証は、鶴見工場の排ガスから三菱重工グループが開発した装置により分離・回収したCO2を、東京ガス横浜テクノステーションに輸送し、メタネーションに利用する実証試験であり、令和4年に3者で締結した協定及び覚書に基づき準備が進められてきたものです。
また、そのメタネーション施設は、再生可能エネルギー100%で運用されています。
さらに、鶴見工場の所在する鶴見区末広町には、様々な生産機能や研究開発拠点が集積しています。メタネーションで生成されるe-メタンや、水素の地産地消モデルの構築など様々な先進的な脱炭素の取組実施を通じて、横浜臨海部における脱炭素イノベーション創出のモデル地区形成を、横浜市はめざしているとのこと。
今後のCCU技術の向上や利用拡大、e-メタンの実用化が大いに期待されます。
仁田まさとしは、カーボンリサイクル技術の向上に取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.652 2023.09.25
読書のいろいろなカタチ
このほど、同窓の先輩らと懇談する機会があり、仕事も一段落し時間が持てるようになり、さて、と考えると「読書」に思い至ったと全集談義になりました。
2019年成立の「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(読書バリアフリー法)を受け、「横浜市社会教育委員会議」が本年2月にまとめた提言に基づく取組として、障がいの有無に関わらず幅広く市民の皆様に読書バリアフリーの理解を深めていただき、助け合い・支え合いの機運を醸成する各種啓発活動が実施されています。
先週9月21日(木)から10月2日(月)まで、読書バリアフリー展が横浜市庁舎2階のプレゼンテーションスペースで開催されています。
また、読書バリアフリー啓発動画の配信や同リーフレットの配布が行われ、「読書バリアフリー情報サイト」が開設されています。
リーフレットでは、バリフリー図書が紹介されています。
<耳で読む>として、本の内容を録音して音声にした音声デイジーや、音声読み上げ対応の電子書籍・オーディオブックがあります。
<目で読む>として、大活字本や、やさしい言葉で分かりやすく書かれたLLブックがあります。
<耳と目で読む>として、本の内容を録音した音声を、その部分の文字や画像をハイライトしながら読むマルチメディアデイジーや、文字情報を音声合成機能で読み上げるテキストデイジーがあります。
<触って読む>として、点字図書や、布・革・毛糸などを用いて触って絵の形が分かるようになっている絵本があります。
バリアフリー図書は市立図書館で窓口または配送により貸し出されています。
また、インターネットサービスとして、市立図書館の「活字資料での読書が困難な方へのサービス」に登録後、「サピエ図書館」に登録して音声デイジー等が利用できます。
仁田まさとしは、読書のバリアフリーに取組みます。
ニッタ マガジン Vol.651 2023.09.18
学校給食に関連する2題
本日は、敬老の日。多年にわたり社会を支えてこられた皆様に、心からのお祝いと感謝を申しあげます。
9月12日(火)の横浜市会で一般質問が行われ、公明党横浜市議団を代表して市来栄美子議員(都筑区)が登壇しました。その中で、学校給食に関連する2題に興味深い答弁を得ました。
一つは、令和8年度から全員喫食となる中学校給食です。
配膳環境の改善策について鯉渕教育長は、
「現在、全ての中学校へ順次、配膳室整備を進めており、今年度は36校で整備が完了する予定です。
併せて、全ての学校でクラス前配膳を実現できるよう、配膳員の増員に加え、整備を早急に進めているエレベーターを利用するなど、学校ごとに異なる設備環境に応じたソフト面・ハード面での対応に取り組み、配膳環境の充実に努めてまいります。」
と具体的に答弁しました。
また、全員給食に向けその姿や価値を、積極的にプロモーションすべきとの主張に対して山中市長は、今後も様々な機会を通じて、給食の持つ価値や魅力を感じていただけるプロモーションを行うと、機運醸成への取組を述べました。
もう一つは、公明党の主張により本年度調査費が計上された学校給食調理室への空調整備です。
検討状況等について鯉渕教育長は、
「現在、給食室の規模や仕様に応じた数校で、回転釜周辺の温度上昇傾向の調査や調理室という特殊な環境においても空調効果を得られる最新型の空調機器の導入検討など、より効果的な手法の検討を行っています。
今後はこれらの調査結果を基に空調機の試行設置を行い、効果について検証していきたいと考えています。」
と、いよいよ試行への考えを示しました。
仁田まさとしは、給食環境の改善に取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.650 2023.09.11
プラスチックごみの分別拡大に向けて
先週の9月7日(木)に始まった横浜市会第3回定例会の本会議において、43日間の会期が決定されました。また、24件の議案が上程され、各会派代表による議案関連質疑が行われました。
計上された補正予算の中には、「プラスチックごみ分別・リサイクル拡大に向けた広報啓発事業」の実施が盛り込まれています。
横浜市では、「脱炭素社会の実現に向けて、現在、分別・リサイクルを行っているプラスチック製容器包装に加え、プラスチック製品も対象とする分別・リサイクルの拡大について令和6年度中に市内一部地域で開始を予定しています。」
現在は、食品トレイ、洗剤ボトル等のプラスチック製容器包装が分別収集されていますが、拡大後はバケツ、洗面器、プランター、食品保全容器、ストローなどのプラスチックのみでできた製品も、同じ収集日に「プラスチック資源」として合わせて収集されます。
この取組による脱炭素社会への市民意識の醸成と具体的な行動変容の効果として、ごみの焼却量が約2万トン削減され、温室効果ガスの排出量が約4.7万トン削減されることが期待されます。
令和6年10月から、中区、港南区、旭区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区で先行実施され、令和7年4月からは全市域で実施が予定されています。
そのために令和6年1月から住民説明会が実施され、店頭、駅頭及びごみ集積場所における広報の準備が始まります。
昨年9月29日に行われた決算特別委員会局別審査において、誰もが分別に困ることがないようきめ細やかな情報提供、丁寧な周知・説明をすべきと主張していました。
仁田まさとしは、プラスチックごみの分別・リサイクルを進めます。
ニッタ マガジン Vol.649 2023.09.04
最近の子育て支援を2題
9月に入り、早いもので本年に入って3分の2が経過しました。依然として真夏日が続く予報となっています。くれぐれもご自愛下さい。
今回は、最近の子育て支援の進捗から2題をご報告します。
ニッタ マガジン Vol.597で、政府が未就園児への支援の一環として、保育所の空き定員等を活用して一週間に1~2日位あずかるモデル事業を、国の予算において20か所程度実施する予定であることを報告しました。
4月に示された国からの通知の後、横浜市内では2園の実施が決まり、このほど、鶴見区と青葉区の各1園でモデル事業が始まりました。
このモデル事業の検証結果を踏まえて、今後、政府の「こども未来戦略方針」に盛り込まれた「こども誰でも通園制度」について検討されます。
もう一つは、就学前のお子さんの預け先に関して保護者の相談に応じ、認可保育所などの様々な保育サービス等について情報提供する保育・教育コンシェルジュについて、オンラインでの相談が、地元南区で始まっている報告です。
保育所の入所等について相談したくても、小さなお子さんがいるので外出がしづらい、区役所まで行くのが大変とのご意見が寄せられていたとのこと。
スマートフォンやパソコンなどカメラ内臓の端末があればWeb会議用アプリ「Zoom」を利用して、自宅や外出先から保育・教育コンシェルジュと互いに顔を見ながら相談することができます。
予約は、横浜市電子申請・届出システムから行います。
仁田まさとしは、誰もが保育所を利用できる仕組みを目指します。
ニッタ マガジン Vol.648 2023.08.28
関東大震災から100年
今から100年前、1923年(大正12年)9月1日11時58分32秒にマグニチュード7.9と推定される関東大地震が発生しました。
近代化した首都圏を襲った唯一の巨大地震であり、死者105,385人、全潰全焼流出家屋293,387に上る被害となりました。地殻を構成するプレート同士が、接触面で一気にずれ動くことにより生じました(内閣府・災害教訓の継承に関する専門調査報告書)。
横浜市でも推定26,623人が犠牲になりました。(横浜開港資料館)
1995年の阪神・淡路大震災では圧死、2011年の東日本大震災では溺死が多いと言われているように一般に大震災での死因には特徴がありますが、関東大震災では焼死が多かったと言われます。要因としては、北上する台風による強風、木造住宅の密集、昼食準備で日を使っている家庭が多かったこと、水道管の破裂もあり、火災が3日間続いたとのこと。
また、津波についても、静岡県熱海市で6m、千葉県相浜(現館山市)で9.3m、州崎で8m、神奈川県三浦で6mの津波が発生したとのことです。
神奈川県立歴史博物館では9月18日(月・祝)まで、「関東大震災-原点は100年前-」と題する展示が行われています。また、横浜開港資料館では12月3日(土)まで、「大災害を生き抜いて-横浜市民の被災体験-」との展示が行われています。
「政府、地方公共団体等関係諸機関をはじめ、広く国民が台風、高潮、津波、地震等の災害についての認識を深め、これに対処する心構えを準備する」ための啓発デーとして9月1日が「防災の日」と制定されました。
このほど、公明党神奈川県本部は「災害時あんしんカード」を作成し、過去の教訓を未来に活かしていくために、防災意識と具体的な行動への啓発活動を進めています。
仁田まさとしは、防災・減災対策に全力で取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.647 2023.08.21
エコ家電購入でポイント還元
連日、厳しい暑さが続いています。先日の台風6,7号でも地球温暖化の影響と思われるこれまでにない風水害が発生しました。
地球温暖化を招く温室効果ガスの削減や家計負担軽減を目的として、「エコハマ(横浜市エコ家電応援キャンペーン)」が、来週8月29日(火)からスタートします。
基準を満たす省エネ家電を購入した市民の方に対して、本体購入価格の20%(上限3万円)分がポイント還元されます。市内登録店舗で購入する必要があります。対象はエアコン、冷蔵庫、LED照明器具の資源エネルギー庁が定める一定の星の数以上を持った家電です。省エネ性能について、エアコンは星3(旧基準で星4)以上、冷蔵庫は451ℓ以上で星3以上、450ℓ以下(冷凍庫含む)は星2以上、LED照明器具は星4以上が基準です。
キャンペーン期間は来年1月末までを予定していますが、予算の上限に達し次第終了する場合があります。
市民向けコールセンターは、045-900-3750(8月28日より)
市民向け特設サイトは、https://ecohama.city.yokohama.lg.jp/(8月29日より)
このキャンペーンにより、市内の約2,200世帯分の年間CO2排出量に相当する約5,800トンのCO2削減が期待されます。
この事業は、公明党提案による地方創生臨時交付金を活用した物価高対策の一環です。公明党横浜市会議員団はこの3月に山中竹春横浜市長へ交付金活用の要望書を提出し、物価高・経済対策を求めていました。
仁田まさとしは、温暖化と物価高対策を進めます。
ニッタ マガジン Vol.646 2023.08.14
大都市制度のあり方調査の一報告
横浜市会の大都市行財政制度特別委員会による調査研究の一環として、州構想を提起した経緯のある新潟県と平成19年に政令指定都市に移行した新潟市を訪問しました。
<州構想と権限移譲>
新しい地方自治制度「新潟モデル」として、平成23年に新潟県と新潟市は共同記者会見を行い新潟州構想が提起されました。
「新潟県と政令市の二重行政解消」や「政令市が有する高度な行政機能を全県に波及」させ、基礎自治体の自治権強化を目指すものでした。
その後設置された新潟州構想検討委員会等を経て、合併、再編という制度の議論ありきではなく、県と新潟市の間の課題整理に特化して協議が行われ、平成28年の地方自治法改正により法定化された新潟県・新潟市調整会議が令和1年まで開かれる経過を辿りますが、その後の構想進展は見られませんでした。
一方で、平成12年の地方分権一括法による自治法改正により、県からの市町村への権限移譲が推進され、令和5年4月現在、県所管事務844項目のうち、181項目が移譲されています。静岡県に次いで全国2位の移譲法律数という状況は、県と市町村の良好な関係を基調とすることが注目されました。
<区自治協議会と住民自治>
平成13年1月の黒崎町と合併、平成17年3月には12市町村と大合併、10月に巻町と合併し、新潟市は平成19年に政令指定都市となりました。同時に分権型政令市に向けて住民と区をつなぐ住民自治推進のため区自治協議会が全8区に設置され、地域コミュニティ協議会や公共的団体の代表、有識者等からなる原則30人以内の委員により構成されています。
「協働の要」と「審議会」としての役割を担い、様々な事業が提案・実施され、課題解決や地域課題の把握・共有などの成果が得られていました。
仁田まさとしは、都市機能の充実に努めます。
ニッタ マガジン Vol.645 2023.08.07
道路ふれあい月間
日本気象協会は、「8月の気温は、平年より高い所が多く、厳しい暑さとなりそう」と示しています。引き続き、熱中症等への厳重な警戒が必要です。
8月1日から31日までは「道路ふれあい月間」となっており、中でも8月10日(木)は「道の日」であることを横浜市は1日に記者発表しました。
それによると、「道路ふれあい月間」は、道路の愛護活動や道路の正しい利用の啓発等の各種活動を特に推進することにより、道路を利用する方々に、道路とふれあい、道路の役割や重要性を改めて認識していただき、道路を常に広く、美しく、安全に利用していただくことを目的としています。
道路の主な役割は、4つ。
①私たちの暮らしを支えています。
毎日の食卓に並ぶ食べ物、生活に欠かせない日用品等が、道路を利用して運ばれています。
②上空や地下に収容しています。
電気、電話、水道、下水道、ガスなど、生活に欠かせないライフラインが収容されています。
③災害時には、避難路として利用されます。
火災の際には、防災帯として、生命、財産を守る重要な役割を果たします。
④住みよいまちづくりのために
通風や採光、緑化などの空間として、役立っています。
令和5年度の「道路ふれあい月間」推進標語の最優秀賞(小学生の部)は、
「気持ちいい 道路であいさつ にっこにこ」です。
また、道路啓発活動の一環として、各種事業の紹介や清掃活動、啓発物品の配布等が行われます。地元南区では、8月15日(火)の13時30分~15時まで南区役所の多目的ホールにて、道路啓発パネルの展示や道路の日リーフレット・啓発物品の配布が行われます。
横浜市には、国道、県道、市道、有料道路を合わせて7,872,953mの道路延長があり、98.4%の舗装延長率まで整備されています。
仁田まさとしは、道路の充実に努力します。
ニッタ マガジン Vol.644 2023.07.31
猛暑と感染症への備えを
連日、猛暑日が続き、熱中症警戒アラートが発表されています。
熱中症の予防について、横浜市ホームページには次のように4つのポイントが示されています。
1つは、水分をこまめに摂取することです。
喉が渇かなくても水分をこまめにとることが大切です。なお、アルコールは利尿作用があるため、逆に脱水を進めてしまいますのでお気を付けください。汗をたくさんかいた時は、スポーツドリンクなどで水分と塩分を補給しましょう。一度にたくさん飲まず、適量を小分けにして飲みましょう。
2つは、服装の工夫です。
襟元を緩め、風通しのよい服装にし、外出時は帽子や日傘を使用しましょう。汗を吸収し、通気性のよい素材の衣服にしましょう。
3つは、暑さを避けることです。
直射日光を避け、日陰を歩くようにしましょう。炎天下や高温多湿下での作業や激しい運動はできるだけ控えましょう。エアコン等の空調を使用し、室内の温度・湿度をチェックしてみましょう。
4つは、日頃からの健康づくりです。
睡眠を十分にとり、バランスの良い食事を心がけ、体調の悪い時は無理をしないようにしましょう。短時間の軽い運動をする習慣をつくり、暑さになれるようにしましょう。
一方で、ヘルパンギーナという感染症について流行警報が発令されています。
ヘルパンギーナは、2~4日の潜伏期間の後、突然の発熱に続いて咽頭痛が出現する感染症です。咽頭粘膜は赤くなり、特にのどの奥に1~2mmの水ぶくれ・潰瘍が出現します。通常は1週間程度で治ります。
感染経路は接触感染・経口感染・飛沫感染で、予防のためには手洗いが大切です。
仁田まさとしは、市民の健康を守ることに努力します。
ニッタ マガジン Vol.643 2023.07.24
行政視察で学ぶ
このほど、横浜市会の国際・経済・港湾委員会で行政視察が行われ、各局関連の事業を調査しました。
<国際局関連>
日本で初めての公立日本語学校が北海道東川町に設立されています。2015年の開校以来、22か国572人の新入生を受け入れています。進路としては、国内の大学や専門学校への進学、日本での就職を希望する学生が増えてきているとのこと。
また、短期日本語・日本文化研修事業が2009年夏からスタートしており、これまでに東アジア諸国を中心に3,300名を超える受講者となっています。外国人サポートの窓口である多文化共生支援室も設立されました。
<経済局関連>
旭川市では「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を2020年に策定し「都市・農村・自然が共創し、ひととしごとが力強く好循環する北北海道の拠点」を目指しています。具体的な施策体系として、
基本目標1:若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
基本目標2:新しい人の流れをつくり、留まれる中核拠点を創出する
を位置づけ、その達成のため、
基本目標3:北北海道を舞台にチャレンジするひとや企業を応援し雇用環境を充実する
基本目標4:安心で魅力ある持続可能な拠点都市を形成する
としています。
札幌市では、産官学の「ALL HOKKAIDO 体制」で複合型・都市型フェスティバルとして「NoMaps」が行われ、クリエイティブ産業の活性化や創業支援・新産業の創造・投資の促進等のための交流の場を形成しています。
<港湾局関連>
港湾取扱貨物量(R3、外貿+内貿)が国内4位の苫小牧港では、ダイヤグラムの改善によるトラックドライバーの働き方改革やカーボンニュートラルポートの形成計画の取組がありました。
仁田まさとしは、事業の研鑽に努めます。
ニッタ マガジン Vol.642 2023.07.17
生徒の安心できる居場所を
このほど公明党横浜市会議員団は、横浜市立橘中学校(保土ケ谷区)を訪問し、不登校生徒支援としての校内ハートフル事業の実施状況を視察しました。
同校では、格技場の一部を活用して校内ハートフル事業が実施され、1日あたり10名前後の生徒が登校していました。
また、同校の特徴として、「地域で地域の子どもを育てよう」との趣旨でNPO法人「居場所そら」が活動しており、学習支援として無料の塾「橘塾」を運営し横浜国大の学生らが携わっています。
校内ハートフル事業とは、在籍している教室への登校は困難ですが、別室であれば登校できる生徒を対象として、校内の特別支援教室等で学習支援など個々の状況にあった支援を実施する事業です。支援員が週5日常駐し、いつでも迎えてくれる「安心できる居場所」として、また、輪番制教科担当による指導のほか、ICTを活用し生徒の特性や能力、興味関心に応じた「個別最適な学び」を提供し、生徒一人ひとりの「社会的自立」を目指しています。
令和5年度には55校で実施予定であり、第4期教育振興基本計画では令和7年度の中学校全校での実施としています。
実施校の9割で、在校日数、在校時間や教職員とのコミュニケーションが増加しているとの成果が見られ、「新たな不登校を生まない取組」としても期待されます。
平成10年9月の本会議一般質問で不登校児童生徒数の増加を取り上げ、その数約1,700人と確認して以来、解消に向けて取り組んでいますが、残念ながら、令和3年度の不登校児童生徒数は6,616人と大きく増加しています。
仁田まさとしは、不登校の課題に挑戦します。
ニッタ マガジン Vol.641 2023.07.10
国へ制度・予算を要望
先週6日に、山中竹春横浜市長が伊佐進一厚生労働副大臣へ国の制度及び予算に関する提案・要望を行いました。
伊佐厚労副大臣からは主な項目の中で、「『出産費用の実質無償化に向け丁寧な制度設計』については、今は国においても議論の過渡期であり、横浜市からいただいた具体的な提案を踏まえて検討したい。『帯状疱疹ワクチン等の定期接種化と財源措置』については、横浜市の要望を受けて、現場のニーズが多いと認識しており、ワクチン接種の有効期間などのデータなどもふまえ検討したい。」とのコメントがあったとのことです。
これに先立ち5月17日、公明党市議団は山中竹春横浜市長に、市から国に対して強く要望すべき13項目を申し入れていました。
①小児医療費助成制度の拡充(高校卒業までの対象拡大)
②児童手当の所得制限撤廃と支給額の拡大
③出産育児一時金の地域実態に合わせた地域加算制度の導入及び保険適用検討における課題と対策の検討
④幼児教育保育の無償化の0~2歳児への適用及び人材確保策の更なる充実
⑤給食無償化の全国一律の制度化
⑥障がい児・者への日常生活用具及び補装具を支給するための支援の拡充
⑦教職員の職場環境改善及び長時間労働の是正(教員給与特別措置法の見直し等)
⑧帯状疱疹予防ワクチンへの補助金導入および定期接種化の検討推進
⑨現場の声をより反映させた介護・認知症対策、人材確保策の充実
⑩EV充電器の普及およびEV車両購入促進への補助事業の拡充
⑪通学路、住宅街、公園等への防犯カメラ設置事業の補助制度の拡充
⑫インボイス制度導入における中小企業への支援の拡充
⑬外国人材との共生に向けた、人口規模に見合った入国管理庁からの交付金の拡充
これらが大きく反映した内容での提案・要望でした。
仁田まさとしは、国とのネットワークで政策実現に取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.640 2023.07.03
横浜特別市を目指して
本年度は、横浜市会の大都市行財政制度特別委員会に所属し副委員長を務めます。この特別委員会では横浜市が目指す新たな大都市制度である「横浜特別市」の実現に向けた調査研究を行います。6月7日(水)には、調査研究テーマを「特別市の法制化に向けた機運醸成について」と決定しました。
横浜市が実現を目指す新たな大都市制度である特別市とは、原則として国が担うべき事務を除くすべての地方の事務を横浜市が一元的に担い、その仕事量に応じた税財源も併せ持つ制度です。
国の事務以外の地方が担う横浜市域の事務については現在、指定都市である横浜市が担っている事務と県が中間関与している事務があります。これにより、窓口が分散し事務処理に時間がかかる場合があり、非効率な二重行政となっています。
事務・権限を市に一元化して二重行政を解消し、市民の皆様に身近な場所で、きめ細かい行政サービスを提供していく必要があります。
また、指定都市は一般の市町村事務に加え、県に代わって保健所など多くの事務を担っていますが、地方税制は事務・権限に関わりなく画一的であるため、県に代わって行う事務に必要な財源については不十分な状況です。
必要な財源が措置されるよう、税源配分の見直しが必要です。
特別自治市となることで、これまでの、子育て支援、医療政策、崖地の安全対策、都市計画、就業支援・雇用対策などの二重行政が解消されサービス向上が期待されます。また、大都市としての総合力と現場力を生かした積極的な政策展開によって経済の活性化が図られます。
実現に向けては市民の皆様のご理解を得ることと、立法化が前提となります。
仁田まさとしは、特別市の広報・周知に努めます。
ニッタ マガジン Vol.639 2023.06.26
関東大震災で自治体間支援
先日参加した地域の懇談会で、関東大震災の際に差し伸べられた関西府県連合等からの震災救護の事実を知りました。
100年前の1923年(大正12年)9月1日、午前11時58分に神奈川県西部を震源とするマグニチュード7.9規模の関東大震災が発生。直接死・行方不明者は約10万5千人(内閣府)と甚大な被害となりました。
地元南区中村地区に神奈川県揮発物貯庫や県第二衛生試験場が設置されていましたが、これらの焼け跡に震災救護関西府県連合が、大規模救護施設を設置しました。
一つは、患者1,000人を収容できる仮病院の建設です。9月10日に大林組が請負契約しました。木材は全て大阪で加工し、現地では組み立てだけをやる計画を立て、大阪市有の2万坪の地所を借り入れ、2,000人以上の職人を動員して昼夜兼行で材料の加工を進め、チャーターされた汽船玄海丸に社長以下多数の社員、大工が乗り、汽船あるたい丸に加工済みの材料を積み込み、社員職工、大阪府の技術者が乗り横浜港に到着(大林組80年史)。
9月26日に工事が完成し、「大阪府外一府六県連合震災救護仮病院」として10月1日に開院したとのことです。
この仮病院は罹災者だけに限らず一般患者も無料で診察・入院できました。10月から12月までの患者数は新患9,192人、再来21,703人、入院患者は1,254人と、多くの人命が救われました。
もう一つは、大阪府外一府五県が、被災者収容のための52棟の居住用バラック、その他小学校2校、村役場、消防署、警察署、公設市場、簡易食堂、図書館閲覧所などを10月27日に完成させました。
紹介した講師の方は、「関西村」と称せられるように至ったこの歴史を忘れないで頂きたいと結びました。
仁田まさとしは、心新たに防災・減災対策を進めます。
ニッタ マガジン Vol.638 2023.06.19
公明の子育てプランの多数が政府案に反映
先週13日、政府より「こども未来戦略方針」が示されました。公明の子育て応援プランによる提言内容が数多く反映されています。
主な施策を紹介します。
① 児童手当については、所得制限を撤廃し、対象を高校卒業までに拡大し、第3子以降は月3万円に増額し、来年10月支給分から実施されます。
② 子どもの医療費助成ついては、自治体による制度拡充の障がいになっている国民健康保険の国庫負担の減額調整措置が廃止されます。横浜では8月より完全無償化され、今後、18歳までの対象を目指します。
③ 高等教育(大学)無償化ついては、授業料減免と給付型奨学金を24年度から多子世帯と理工農系学生の中間層(世帯年収約600万円)までに拡充されます。
④ 出産・子育て応援交付金(10万円)については、22年度に創設されましたが、求めている事業の恒久化に向けて戦略方針に“着実に実施”と位置付けられました。「伴走型相談支援」とセットで進めます。
⑤ 出産費用については、26年度をめどに保険適用に向けて検討されます。
⑥ 保育所利用については、就労要件を問わず専業主婦でも時間単位で利用できる「こども誰でも通園制度」(仮称)が創設されます。
⑦ 育児休業給付金については、休業前賃金の手取りで8割相当を10割相当に、25年度開始目標で引き上げられます。
その他、子ども貧困対策、虐待防止、障がい児や医療的ケア児への支援拡充など、きめ細かな内容となっています。
財源は、徹底した歳出改革などで実質的な追加負担はなく、財源確保のための増税も行いません。28年度までに「改革工程表」を策定し、安定的な財源を確保します。また、関連予算を一元管理する特別会計「こども金庫」の新設も盛り込まれました。
仁田まさとしは、さらに子育て・教育への支援を進めます。
ニッタ マガジン Vol.637 2023.06.12
コロナ後遺症の現状と今後
新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、5類に移行してから約1か月が経過しました。
6月10日付け公明新聞に平畑光一医師へのコロナ後遺症に関するインタビュー記事が掲載されました。平畑医師はこれまで約6000人の後遺症患者を診察されてきており示唆に富む内容ですので一部を抜粋してご紹介します。
-コロナ後遺症とは。
世界保健機関(WHO)はコロナ後遺症を「2か月以上持続し、他の疾患では説明できない症状」と定義している。ただ、臨床上はできるだけ早く検査を行い治療を始めることが望ましい。
-5類に移行したが。
ウイルスの危険性が変化したわけではない。倦怠感など後遺症患者は依然多く、警戒が必要。
-後遺症の注意点は。
コロナ感染から2か月間は、無理をしてはいけない。疲れないように生活することが大事だ。
-新しい治療法の開発は。
喉の奥に薬品を直接塗り付ける「上咽頭擦過療法」や呼吸器のリハビリテーションなどで回復が望める。漢方薬やはり治療が効くケースも多い。
-直面する課題は。
5類に移行しても、後遺症発症のリスクは変わらないという認識を社会全体で共有することだ。
-行政に対しては。
後遺症の特徴や診療のポイントなどを学べる場を設けるのは大切だ。
公明党の訴えにより改定された厚生労働省の後遺症の診療手引き「罹患後症状のマネジメント」の影響は大きい。継続的な拡充が必要だ。さらに、後遺症の原因や治療法の解明も急務だ。
令和5年3月8日の横浜市会健康福祉・医療委員会でコロナ後遺症への取組を取り上げ、医療機関の情報共有強化等を主張しました。
仁田まさとしは、コロナ後遺症への取組を進めます。
ニッタ マガジン Vol.636 2023.06.05
1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭
先週2日(金)に横浜市は、第62回「1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭」の開催を発表しました。
開催日時は8月20日(日)午前5時50分から7時30分まで、赤レンガパークを会場(荒天時は横浜武道館)として行われ、NHK総合テレビ・ラジオ第1で生放送されます。
体操指導はNHKテレビ・ラジオ体操指導者の鈴木大輔氏、ピアノ演奏は同演奏者の能條貴大氏が担当します。
5時50分に開会し横浜市長挨拶等ののち、6時30分からラジオ体操・みんなの体操が始まります。7時からアトラクションとして横濱中華學院交友會による龍舞が披露され、7時15分からお楽しみ抽選会が行われ閉会の予定です。
主催は、株式会社かんぽ生命保険、NHK、NPO法人全国ラジオ体操連盟で横浜市が共催します。
参加費は無料ですが、事前申込制により6月20日(火)から7月19日(水)に申込の受付が行われます。
「1000万人ラジオ体操・みんなの体操祭」は、「夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」の中央行事として、1962年から始まっています。
2009年にも赤レンガパークで行われ、2020年にも予定されましたが新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行の影響で中止されています。
ラジオ体操は第一も第二も13種類の運動があり、どちらも3分間ですが、しっかり行うと全身で650ほどの筋肉のうちの400ほどが刺激できると言われており、運動不足の解消に適しています。
仁田まさとしは、健康増進とにぎわいづくりに努めます。
ニッタ マガジン Vol.635 2023.05.29
よこはま笑顔プランへのご意見を
先週26日より、横浜市地域福祉保健計画(素案)(愛称:よこはま笑顔プラン)へのパブリックコメント(意見募集)が6月27日まで行われています。
よこはま笑顔プランは、令和6年度から令和10年度までの5年間を計画期間として、「誰もが安心して自分らしく健やかに暮らせる『よこはま』をみんなでつくろう」を基本理念に、次の3項目の“目指す姿”を定めています。
1.認め合い
~お互いに尊重し、安心して自分らしく暮らせる地域~
2.つながり
~気にかけあい、支えあい、健やかに暮らせる地域~
3.ともに
~助けが必要な人も、手を差し伸べる人も、ひとりで抱え込まない地域~
その推進のための取組は、
1.身近な地域で支えあう仕組みづくり
1)日常的なつながりを通じた住民による支えあいの充実
2)課題解決に向けた住民・関係機関・団体の連携
3)身近な地域における総合的な権利擁護の推進
4)生活困窮者支援を通じた地域づくり
2.地域における福祉保健活動を推進するための基盤づくり
1)地域における関係組織・団体の体制の強化
2)社会福祉法人・企業・学校等の主体的な参画に向けた支援
3)区役所・区社協・地域ケアプラザ等の協働による地域を支える基盤づくり
3.多様性を尊重した幅広い市民参加の促進
1)多様性を理解し、尊重しあえる地域づくり
2)交流・つながり、社会に参加する機会の創出と拡充
3)つながりを通じた健康づくりの推進
詳しい内容は横浜市健康福祉局福祉保健課のホームページをご覧ください。
仁田まさとしは、地域福祉保健事業の充実に努めます。
ニッタ マガジン Vol.634 2023.05.22
物価高対策を進めます
いよいよ神奈川県議会や横浜市会が始まり、国において閣議決定された地方創生臨時交付金の増額分を活用した物価高対策案が示されました。
公明党横浜市会議員団が3月16日に山中横浜市長へ提出した要望が具体的にカタチとなっています。
県の補正予算案に、LPガス料金の高騰に対する支援(上半期)として一般消費者等の負担を軽減するために、LPガスの県内販売事業者による利用料金の値引き支援金の支給が計上されました。支援額は、一契約あたり月380円の半年分である2,280円となります。
横浜市の補正予算案に計上された主な事業は次の通り。
*住民税非課税世帯に、電力・ガス・食料品等の価格高騰を踏まえた給付金(3万円/世帯)をプッシュ型で給付。
*一定の省エネ評価を満たすエアコン、冷蔵庫、LED照明器具の購入金額を20%(上限3万円)還元。
*商店会等が発行するプレミアム付商品券への補助、広報活動やイベント等来街促進に取組む商店街への経費を補助。
*小中学校の給食の物資購入費について当初想定より上回る購入委託費を補正。
*子ども食堂等の子どもの居場所を運営する取組に支援金を交付。
*保育所や幼稚園など各種児童福祉施設の光熱費等及び食材費の物価高騰の影響分を補助。
*社会福祉施設等の光熱費等及び食材費の支援について物価高騰の影響分を補助。
*市救急医療体制参加病院への支援。
*中小企業の省エネルギー機器導入に助成するグリーンリカバリー設備投資助成事業を増額。
また、専決処分により、すでに低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(児童一人につき5万円)の給付が4月27日から順次行われており承認が求められています。
今後の議会での議論を経て実施に向かいます。
仁田まさとしは、国県市のネットワークで物価高対策に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.633 2023.05.15
30年以内の地震発生確率に思う
5月に入って半月が経過しますが、この間、大きな地震が3度も発生しています。
5日に、石川県能登地方を震源として最大震度6強の地震。11日には、千葉県南部を震源とする最大震度5強の地震。そして、一昨日の13日には、鹿児島県・トカラ列島近海を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。
対岸の火事とすることなく、あらためて地震への備えを実行に移さなければと思います。
南海トラフ巨大地震について政府の地震調査研究推進本部は、長期確率評価による発生確率を30年以内に70~80%としています。
また、国立研究開発法人防災科学技術研究所は、地元南区の30年間に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率を85.2%と示しています。
各地で防災講座が定評の松井一洋広島経済大学名誉教授(防災士)は著書の中で、
「ある研究者に、『統計モデル(ポアソン過程)としての30年という期間(一つの区切り)は、被災想定地域が大災害への備えを充実するのに相当な期間ではないか』という指摘を受けたことがあります。」と述べています。
果たして、30年という期間は「大災害への備え」を充実させているのかしっかり見極める必要があります。死者6,400余名の被害をもたらした阪神・淡路大震災から28年余が経過していますが、「大災害への備え」は道半ばと実感しています。ましてやこの間に東日本大震災を経験してもなお、家具の転倒防止や感震ブレーカー等の備えの加速度は残念ながら体感し得ません。
30年という確率的な合理性を認めつつ、社会的な緊張感の弛緩に立ち向かい地域の防災力を加速度的に高める啓発を不断に模索する努力が求められます。
今年は関東大震災の発生から100年が経過したことも随所で語られています。
仁田まさとしは、地震対策に全力で取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.632 2023.05.08
“もの忘れ検診”が50歳から無料で
本日より、新型コロナウイルス感染症の分類が2類から5類に移行することになり、外出の自粛や感染防止対策などが、個人の判断に委ねられることになります。
また、65歳以上の方や基礎疾患のある方などを対象に、ワクチンの個別接種が始まります。
横浜市では令和3年度から、認知症の早期発見・対応のため、65歳以上の方を対象に、“もの忘れ検診”(認知症の簡易検査)が無料で実施されています。160か所の市内医療機関で受診可能となっており、地域ケアプラザ等で配布のチラシや市ホームページで確認できます(「横浜市 5年度 もの忘れ検診」で検索)。
認知機能などを確認する問診であり、年に1回の検診が推奨されています。
認知症の疑いがあった場合で、専門医療機関の受診が必要な場合は(有料で)紹介を受けることもできます。
この“もの忘れ検診”の対象年齢が本年4月1日(土)より、50歳以上に拡大されました。令和6年3月31日(日)までを実施期間として、41か所の医療機関で実施されています。
認知症は早い気づきと対応が重要であり、“もの忘れ検診”により、認知症の疑いのある方を早期に発見し、早期の診断と治療につなげることが期待されます。
65歳未満で発症する認知症である若年性認知症の人数は、18歳~64歳人口の10万人当たり50.9人とされており、横浜市では約1,160人と推計されます。50歳以上から有病率が拡大する特徴を有しています。
若年性認知症の方や家族への支援を行うために、「若年性認知症支援コーディネーター」が4か所の認知症疾患医療センターに配置されています。
仁田まさとしは、認知症疾患対策に全力で取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.631 2023.05.01
新たに2つのフェーズへ
本日、4月9日の横浜市会議員選挙により当選した議員が初登庁し、全員構成による初市会協議会に臨みます。
公明党横浜市会議員団は15名となり、先の同準備会において第2会派が決定しています。
頂きました4年間を大事に、市民の皆様からの附託にお応えすべく、政策実現に全力で取り組む決意です。
また、5月8日(月)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が、2類から5類に移行することになります。これにより行政による行動制限は無くなり、外出の自粛や感染防止対策などが、個人の判断に委ねられることになります。
4月28日には横浜市新型コロナウイルス対策本部会議が開催され、山中竹春横浜市長が次のコメントを発しています。
「手洗いや換気、三蜜の回避、場面に応じたマスクの着用など、基本的な感染防止対策を行うとともに、感染への備えとして、抗原検査キットや解熱鎮痛薬を常備していただくようお願いします。」
そして、「5月8日からは、65歳以上の方や基礎疾患のある方などを対象に、ワクチンの個別接種が始まります。重症化を防ぐため、接種を積極的にご検討ください。」
さらに、「5月8日以降も、感染症コールセンターを24時間稼働させ、市民の皆様の不安や疑問にお答えします。また、ホームページなどで感染防止対策等の情報をお届けしていきます。
さらに、感染の再拡大に備え、Y-CERTによる入院調整を継続し、安定的な医療提供体制を維持するとともに、ワクチン接種の推進など、引き続き、気を緩めず取り組んでいきます。
仁田まさとしは、心新たに議会に臨み、市民の安全・安心を守り抜きます。
ニッタ マガジン Vol.630 2023.04.24
政策実現に邁進
前半戦に続き、昨日投開票された統一地方選挙の後半戦も、公明党神奈川県本部42名の候補が全員当選させて頂きました。
党員・支持者の皆様の献身的なご支援に心から感謝申し上げます。
今週で任期を終え、5月1日に次期の初登庁となります。
4月9日までに強く訴えた主な内容を改めて確認します。
実績の中で、特に2項目。
学校体育館に、4年前はゼロであったエアコン・空調設備が、今年度までに113校の市立小中高・特別支援学校に設置されることを報告し、今後、早期に500校を超える全校に整備することを訴えました。
また、小児医療費助成制度について、1992年に横浜市会ではじて公明党が提案し毎年の予算編成のたびに粘り強く対象年齢の拡大に努め、この8月には中学3年まで無償化が実現することを報告し、今後、高校3年までへの対象年齢の拡大を訴えました。
この実現力を活かし、次に目指すお約束は特に2項目。
一つは、「帯状疱疹に負けない横浜」にすること。同年度予算にも市内の罹患状況等の基礎データ把握のための調査費が計上されています。
山口党代表も、この選挙戦でも帯状疱疹の発症や重症化を予防するワクチン接種への公費助成に言及。公明のネットワークによる東京都内の公費助成の事例に触れながら、今後は、国の定期接種に位置付けることで「無料で接種できるように(中略)公明党にやらせてもらいたい」と訴えています。
もう一つは、スマホを持っていない方々への防災情報のプッシュ型配信サービスの提供です。専用端末がテレビを自動で立ち上げて、文字、画像及び光と音声で「地震がきます!」等の情報を知らせる仕組みの実現を主張しました。
仁田まさとしは、お約束の実現に全力で取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.629 2023.04.17
提案から実証実験へ
先週12日に、横浜市会議員選挙の当選が告知され証書が授与されました。
新たに4年間の任期を頂き、身の引き締まる思いでいっぱいです。政策実現に向け全力で取り組んでまいります。
本日17日(月)から、「ローソン上郷八軒谷戸店」と「ローソンLTF三ツ境店」の2店舗で、公共トイレ協力店(愛称:「ありがトイレ」)の取組みが開始されました。
横浜市では、市民の皆様が身近にあるコンビニエンスストア等のトイレを気軽に利用でき、安心して外出ができる環境を整えられるよう、公共トイレ協力店の検討を進めており、この度、株式会社ローソンからの協力が得られ、実証実験が始まりました。
今後、取組の効果が検証されることになります。
実施店舗には、実証実験に協力を頂いていることがわかるように、店舗出入口等にステッカーが提示されます。
ご利用の皆様は、店舗にひと声かけてご利用いただくようお願いいたします。
この事業は、令和4年3月に行われた環境創造・資源循環委員会にて、市内の不足する公衆トイレの機能拡大策として、コンビニ等の民間との協力による公共トイレ協力店の取組みを提案したことから検討が始まったものです。
局長からは、「まず一歩を踏み出していきたい」との前向きな答弁を得ていました。
仁田まさとしは、“外出時のトイレに困らない環境づくり”に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.628 2023.04.10
横浜市議選の当選を受けて
この度の横浜市会議員選挙南区選挙区で、11,937票を頂き、3位で当選させていただきました。本当にありがとうございました。
横浜市でも既に"高齢社会"に突入している実情を踏まえ、人生100年時代を見据え誰もが安心していつまでも生きがいを持ち暮らせるまちづくりを進めていく必要があると感じております。
選挙期間中には、今後の取組むべき課題として、80歳までに3人に1人が罹患すると言われる帯状疱疹のための予防ワクチンの接種を公的支援することや、災害情報をプッシュ型配信するシステムの構築を訴えました。
これからも激甚化するであろう災害にあっては、現在スマートフォンをお持ちでない方々へのプッシュサービスとして、テレビが自動的に立ち上がり、災害情報を光や音でお知らせするといったシステム作りが命を守るうえで必要になってきます。
誰一人取り残されることのないSDGs横浜を目指してまいります。
出生からお亡くなりになるまで、身近なところで寄り添う市民の代表として次の4年間もひた走ってまいる決意です。
選挙期間中に発生した南区内での火災により犠牲者になられた方へ心からのご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様にお見舞い申し上げます。
仁田まさとしは、本日からの4年間、政策実現に全力で取組みます。
ニッタ マガジン Vol.627 2023.03.27
認知症疾患医療センターの区内設置を目指して
人生100年時代に向けて、大きな課題の一つに認知症があります。
認知症とは、いろいろな原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなったために様々な障害が起こり、生活する上で支障が出ている状態(およそ6カ月以上継続)を指します。
脳の細胞が壊れることによって直接起こる症状が記憶障害、見当識障害、理解・判断力の低下、実行機能の低下など中核症状と呼ばれるものです。これらの中核症状のため周囲で起こっている現実を正しく認識できなくなります。(厚労省:認知症を理解する)
団塊の世代が75歳を迎える2025年には約700万人(65歳以上の高齢者のおよそ5人に1人)が認知症になると予測されており、人生100年時代と言われる高齢社会では認知症の取組みがますます重要となります。
認知症に関する医療提供体制の中核となる認知症疾患医療センターは、かかりつけ医や保健医療・介護機関等と連携を図りながら、認知症疾患に関する鑑別診断、周辺症状及び身体合併症への急性期対応、専門医療相談などを行う機関であり、地域保健医療・介護関係者等への研修等も行います。
公明党市議団は、その認知症疾患医療センターの増設を推進し、令和3年3月には市内9か所、2区に1か所の体制となりました。
今後は、地元南区をはじめ市内18区への設置を目指します。
仁田まさとしは、認知症疾患施策の充実に努めます。
<追伸>
3月31日(金)は、統一地方選挙の告示日となります。公職選挙法によりメールを使用し選挙運動は禁止されており、無用な誤解を生じることを防ぐため来週の配信は控えさせていただきます。
ニッタ マガジン Vol.626 2023.03.20
公明のネットワークで物価高対策
先週15日、公明党の石井啓一幹事長は岸田文雄首相に対して物価高騰から国民と事業者を守り抜くための追加策を申し入れました。
公明党の取組みのポイントは次の3点。
一つは、電気・ガス代への対応です。
既に電気代は1月使用分から家庭向けで1キロワット時当たり7円の値引きが実施されていますが、大手電力7社が国に値上げを申請していることについて、「安易な値上げは許さない」との立場から、厳格な審査を求め、それでも大幅な値上げが行われる場合は、値引き単価の上積みなどの対応に取組みます。
また、同様に都市ガス代は1立方メートル当たり30円の値引きが行われていますが、加えてLPガス(プロパンガス)の料金負担の軽減策の実現を提案しました。
二つ目は、物価高が家計への影響が大きい低所得世帯や子育て世帯への支援です。
子どもの生活を守り抜くためにも低所得世帯に現金給付を実施すべきと主張し、岸田首相が「検討する」と表明しました。これにより、低所得世帯には一律3万円の支援、ひとり親世帯などには児童1人当たり5万円の給付が実現の見通しとなりました。
三つ目は、自治体独自の対策拡充に向けて、財源となる地方創生臨時交付金の拡充です。
これまで、公明党の地方議員が議会や首長に具体策を提案し対策が実現してきました。しかし、長引く物価高で自治体の財源は枯渇しており、地方創生臨時交付金の積み増しを政府に要請しています。
この提言の翌16日には公明党市議団が山中横浜市長に対して、「物価高騰から市民生活を守るための緊急要望書」を提出し、対策を講じるよう求めました。
仁田まさとしは、横浜市に最適な物価高対策を具体化します。
ニッタ マガジン Vol.625 2023.03.13
PPAによる太陽光発電設備の整備
先週の3月11日で、東日本大震災から12年目となりました。改めて「風化と風評」の2つの風に立ち向かうことを思い起こし、人間の復興に向けての意を新たにしました。
東日本大震災から得られた教訓の一つに、電源の自立化があります。かつて横浜市が、環境未来都市を目指すべきと思い至り推進したことも、被災地では必要な電力をいち早く確保することが復旧の要であると感じたからでもありました。
現在、横浜市では公共施設への太陽光発電設備の導入を進めています。2023年度(令和5年度)予算案には、小中学校等の37校へ導入するための予算が計上されています。
その導入には、2つの特徴があります。
一つは、PPAモデルを採用していることです。
PPA(Power Purchase Agreement)とは、電力販売契約という意味で第三者モデルともよばれています。企業や自治体が保有する施設の屋根や遊休地を事業者が借り、無償で発電設備を設置し、発電した電気を企業・自治体が施設で使うことで、電気料金とCO2排出の削減ができます。設備の所有は第三者(事業者または別の出資者)が持つ形となりますので、資産保有をすることなく再エネ利用が実現できます。(環境省ホームページ)
つまり、初期費用ゼロで太陽光発電設備が導入されることになります。
もう一つは、太陽光発電システムに加えて蓄電池システムを導入することで、非常用電源としての機能を確保できることです。
これによって、自立運転機能を備えることができます。
地元南区では、2023年度(令和5年度)の予定を含めて、5校の小中学校と2校の高校への導入となります。
災害時には避難所となる体育館への非常用電源としての活用が期待できます。
仁田まさとしは、非常用電源の確保を推進します。
ニッタ マガジン Vol.624 2023.03.06
多文化共生のさらなる推進
先週に続き、横浜市会予算特別委員会の国際局審査の報告です。
横浜市内には、10万人を超える在住外国人が生活し、地元南区にも約1万1千人(100か国)の方々が暮らしており、外国人が日本人と地域社会で隣人として生活を送ることが当たり前になっていると考えます。
そのために、共生に向けては外国人の抱える生活課題をいかに解決していくのか。中でも言葉の問題で地域社会に馴染めないことによるメンタル面への影響も少なくないことから、必要な医療に適切につながるサポートを求めました。
国際局長からは、受入可能な医療機関の紹介に加え、電話通訳や通訳ボランティア派遣により、医療機関で安心して診療が受けられる環境整備に努める旨の答弁を得ました。
一方で、事業者の皆様の現場の声を踏まえると、海外からの人材の呼び込みについて、これまで、本格的な取組を早期にスタートさせるよう主張してきました。外国人材を横浜に呼び込むために、現在、市内で活躍する外国人材を対象とした満足度調査等を継続的に行うことが重要と訴えました。
また、外国籍の方が活躍できる場を増やし、様々な市民、団体と連携するため、ワンストップの対応窓口を充実させることも求めました。
さらには、横浜市の多文化共生を推進するための組織体制をさらに強化すべきと主張しました。
国際局長は、包括的な調査については、継続的に行うべきとの認識が示され、地域における外国人材の活躍の場の創出、外国人を含む地域の多文化共生の担い手の連携・協働の強化地に取組む考えが明らかとなりました。
さらに、多文化共生を推進するための体制強化については、副市長より、専任の多文化共生の担当課長を設置するなど、更に体制を充実していくとの答弁がありました。
仁田まさとしは、外国籍住民への支援の充実を推進します。
ニッタ マガジン Vol.623 2023.02.27
ウクライナ侵略から1年を経過して
連日、2023年度横浜市予算案を審議する予算特別委員会が開かれており、この20日に行われた国際局審査で質疑を行いました。
ロシアによるウクライナ侵略から1年が経過しました。依然として戦禍が続いており、未だに多くの命が失われています。あらためて、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、被害にあわれた皆様にお見舞いを申し上げます。
質疑の中で、ウクライナ避難民の支援を取り上げました。
市会では昨年3月23日に「ロシアによるウクライナへの侵略を避難するとともに、国際紛争における武力行使の根絶を求める決議」を行いました。
この決議には、「避難民の受入態勢づくりに率先して取り組む」ことが表明されており、市はこれに応える形で、4月中旬にオール横浜支援パッケージを発表し、4月28日は避難民の拠点施設となるウクライナ交流カフェ「ドゥルーズィ」を開設しました。“ドゥルーズィ”はウクライナ語で友だちとの意味です。
過日、「ドゥルーズィ」を訪問し、施設を利用する避難民の皆様と意見交換し、「医療にかかる際にもサポートしてくれて安心」「友人とも会えて情報交換でき、寛げる」などの声を伺い、母国語で交流できる居場所の重要性を認識しました。
国連をはじめ国際社会の懸命な努力にもかかわらず長期化の様子を呈しており、避難生活も中長期化するなか、支援をもう一歩進めて避難民の“活躍”をサポートする取組が必要と主張しました。
国際局長からは、「ドゥルーズィ」等も活用しながら、オール横浜で寄り添ったサポートを続ける旨の答弁がありました。
仁田まさとしは、ウクライナ支援の充実を求めていきます。
ニッタ マガジン Vol.622 2023.02.20
帯状疱疹ワクチンの定期接種化に向けて
今定例会に上程されている令和5年度の横浜市予算案に、「帯状疱疹予防ワクチンの定期接種化に向けた市内罹患状況等調査の実施」として、百万円の予算が計上されました。
帯状疱疹(たいじょうほうしん)とは、水ぶくれを伴う赤い発疹が帯状に出る皮膚の疾患です。強い痛みを伴うことが多く、症状は3週間から4週間ほど続くと言われています。
子どもの頃にかかった水疱(いわゆる、“みずぼうそう”)ウイルスが体の中で長期間潜伏し、免疫が低下した際などに帯状疱疹として発症します。
発症率は50歳以上から高くなり、80歳までに約3人に1人が発症するといわれています。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の約2割の方に長期間痛みが残る帯状疱疹後神経痛(PHN)になる可能性があるとのことです。
帯状疱疹の予防にはワクチン接種が有効とされていますが、任意接種のため費用は全額自己負担であり、公費でのワクチン接種を求める声が寄せられています。
国では、一定程度の効果は認められていますが、引き続き専門家による定期接種化への検討が進められています。
公明党横浜市議団は、令和4年10月に山中竹春横浜市長に対して、早期の定期接種化と全額国費負担による接種について国への働きかけを要望しました。
その結果、市は同年11月に定期接種化に向けた検討を早急に進めるよう国に対して要望書を提出し、12月には市長から厚労副大臣に直接要望を行いました。
令和5年度予算案への調査費の計上により、国の検討が速やかに進むよう、市内の罹患状況等の基礎データを把握するための調査が行われることになります。
仁田まさとしは、帯状疱疹の予防施策を推進します。
ニッタ マガジン Vol.621 2023.02.13
横浜の教育が目指すべき姿へ
横浜市会の今定例会に、第4期横浜市教育振興基本計画(2022年度~2025年度)の原案が議案として上程されています。
横浜教育ビジョン2030のアクションプランとして、施策・取組みを定めるもので、全体で110ページ(A4)となっています。
計画の視点として、次の3点を示しています。
<一人ひとりを大切に>
子ども一人ひとりの個性や多様性を大切にし、「だれもが」「安心して」「豊かに」の人権尊重の精神を基盤とする教育を推進するとともに、それぞれの資質・能力を育成します。
<みんなの計画・みんなで実現>
複数で子どもに関わる体制の徹底及び、家庭・地域・関係機関・民間企業・NPO等との連携・協働により、チーム横浜で子どもを育てます。
<EBPMの推進>
「横浜市学力・学習状況調査」等のデータ分析により授業改善や児童生徒理解を一層推進するとともに、客観的な根拠に基づく教育政策を子どもの成長に関わる人と共有し、連携して質の高い教育につなげます。
計画の体系には、8つの柱とそれぞれに施策を定めています。
柱1 一人ひとりを大切にした学びの推進
柱2 ともに未来をつくる力の育成
柱3 豊かな心の育成
柱4 健やかな体の育成
柱5 家庭・地域等の多様な主体との連携・協働
柱6 いきいきと働き、学び続ける教職員
柱7 安全・安心でより良い教育環境
柱8 市民の豊かな学び
現在、常任委員会で質疑されており、15日の本会議での議決により、計画が確定されることとなります。
仁田まさとしは、「自ら学び 社会とつながり ともに未来を創る人」の育成に努めます。
ニッタ マガジン Vol.620 2023.02.06
学校へのエアコン設置を次のステージへ
普通教室、特別教室等へのエアコン設置を完了している横浜市立の小中学校では、空調設備について次のステージに踏み出しています。
一つは、学校体育館への空調設備の設置です。
学校体育館には、それまで空調設備は設置されていませんでしたが、公明党横浜市会議員団の強い要請により、2019年より学校体育館に空調設備の設置が始まっています。
学校体育館は、教育活動の重要な施設であるとともに、災害時には避難所となります。これまで、夏の気温の高い中で避難所が開設されたことで、熱中症などの二次災害が起きた事例があります。
2019年に小学校の体育館にエアコンが2校に設置され、大型冷風扇が1校配備されて以来順次拡大され、2023年度予定を含めて、小学校の81校、中学校の26校、特別支援学校の6校の体育館と、合計113校に空調設備が整うこととなります。
これからも、できるだけ早期に全校設置へと進むよう取り組みます。
もう一つは、小学校の給食調理室への空調整備です。
回転釜などの大きな熱源のある給食調理室では、夏に近づくと室内が高温となり、調理員の皆様の体調管理が大変難しいとの状況がお声として寄せられています。
昨年10月、公明党横浜市会議員団は「小学校給食調理室の労働環境改善のため、労働安全衛生法に準じてエアコンの設置」を横浜市長に予算要望しました。
2023年度予算案には、建替え等を当面行う予定がない学校の給食室について、効果的なエアコン設置方法などを検討するための「給食室空調整備検討費」として500万円が計上されました。様々な課題について、他都市事例や学校現場の声を参考に熱中症対について検討されることとなります。
仁田まさとしは、学校の空調設備設置の完結に向けて取組みます。
ニッタ マガジン Vol.619 2023.01.30
テレビ・プッシュサービスに期待
横浜市では、災害時の情報伝達の強化に向けて、テレビ・プッシュサービスの実証実験を令和4年10月から明日まで行っています。
テレビの電源がOFFでも、専用端末がテレビを自動で立ち上げ、文字、画像及び光と音声で「地震がきます!」などの情報を知らせます。また、地上波放送や録画番組を見ていても、自動で画面を切り換え、情報を知らせることができます。
現在、災害時の緊急情報は、テレビ、ラジオ、緊急速報メール、Yahoo!防災速報、Twitter、防災情報Eメール、市ホームページ、広報車、防災スピーカーなどを組み合わせて伝達していますが、スマートフォンを使用していない方への伝達手段について、災害情報の量や即時性について課題がありました。
横浜市民の防災・減災の意識取組に関するアンケートでは、多くの皆様がテレビから緊急情報を取得しているとの結果があり、テレビにより情報伝達をプッシュ型で伝達する手段が検討されてきました。
それを実現するシステムとして、「地域広帯域移動無線アクセスシステム(地域BWAシステム)」があり、その活用により地域公共サービスの向上に取組む民間企業と横浜市が協定を締結しています。
地域BWAは、テレビプッシュ・サービスのほか、地域BWAモバイルルータを区役所、避難所へ整備し、災害時や緊急時の行政間の通信環境を強化することができます。また、避難所へ地域BWAを利用したWi-Fi環境を提供することで避難住民向けの通信環境を強化することができます。
仁田まさとしは、災害時の緊急情報の伝達強化に努力します。
ニッタ マガジン Vol.618 2023.01.23
市立高校を訪問して
このほど、横浜市立みなと総合高校を視察し、校長先生らと意見交換しました。
同校は、「人間力を高める」との教育目標のもと、「学ぶ力を伸長する学校」、「キャリア形成を支援する学校」、「コミュニケーション力を高める学校」との学校像を目指し、「蓄積した知識を活用することができる生徒」、「将来の展望を拓くことができる生徒」、「温かな人間関係を築くことができる生徒」との生徒像を目指しています。
教育活動の特色としては、「産業社会と人間」「総合的な探究の時間」「多様な選択科目」を連携しキャリア教育の充実を図り、生徒の将来の夢の実現を図るため特色ある選択科目を設け「プラスαを学ぶ」ことをコンセプトとしています。 その実現のために、1年次の共通履修科目から2年次では約半数の選択科目、3年次では2/3の選択科目の履修を可能としています。「プラスαの学び」を保障する総合選択科目は、「文化・生活」「科学・社会」「国際」「情報」「ビジネスマネジメント」の5つの系列が用意され生徒自身が組立て学ぶことができます。 本年4月から開かれる関東学院大学の横浜関内キャンバスでのカリキュラムの履修も検討されているとのこと。 また、国際理解教育、国際交流プログラム等によりコミュニケーション力を高め、国際性の向上が図られています。バンクーバー市と上海市にある2つの高校と姉妹校提携しています。 キャリア教育では、1年次の「産業社会と人間」、2・3年次の「総合的な探究の時間」を通して卒業後の進路、生き方を探究することができ、「自分の将来は自分で決める」ことに注力しています。
横浜市が高校を設置する意義を不断に問う必要があると考えます。
仁田まさとしは、豊かな高校教育をめざします。
ニッタ マガジン Vol.617 2023.01.16
中学生校外活動支援の利用者が拡大
2022年4月から12月までの9か月間の「中学生校外活動支援運賃制度」の利用実績について市交通局より報告を受けました。
利用件数は1,130件、乗車人数は12,094人でした。
2022年度は3か月を残していますので、2021年度(2021年4月~2022年3月)実績である756件、7,232人より倍増するペースで利用されています。
多くの中学生がこの制度を利用して校外活動が行われています。
「中学生校外活動支援運賃制度」は、校外活動を行う中学生(公立・私立を問わず、人数要件なし)を対象に、横浜市営地下鉄運賃を50%程度割引きし小児運賃と同額で乗車できる制度です。適用日は、土休日と長期休業期間(4/1~4/4、7/21~8/26、12/26~1/6、3/26~3/31)です。利用には学校長発行による校外活動実施証明書が必要となります。
この制度が生まれたのは、中学校のPTA会長を経験されたTさんのお声が始まりです。
2017年の秋にTさんから、「中学生の部活動で移動にかかる運賃が負担となっている。例えば競技大会や練習試合などの遠征のたびに多くの出費を余儀なくされている。せめて義務教育の間は、小学生のように半額で活動できないか?」と、ご相談を受けました。
早速、距離に応じて運賃が設定されている市営地下鉄運賃の割引について、交通局に検討を要請しました。
検討を申し入れた約1年後に交通局より、団体乗車券制度の拡大を基本に検討する旨の考えが示され、具体的な仕組みをさらに協議して来きました。
そして、令和2年度から運用が開始されたものです。
仁田まさとしは、市民の声の実現に努めます。
ニッタ マガジン Vol.616 2023.01.09
出産・子育てを伴走型で応援
本日は、成人の日。新成人の皆様に、心からお祝いを申し上げます。
前号に続き、昨年12月の定例会報告です。
「出産・子育て応援事業」のための34億9千万円余の補正予算が成立しました。
この事業は、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援が一体で実施されるものです。
経済的支援として、妊娠届時に妊婦一人あたり5万円(出産応援金)、出生届出時に新生児一人あたり5万円(子育て応援金)の合計10万円が支給されます。
出産応援金の対象は、
①2022年4月1日から2023年3月31日までに妊娠した方。
②2022年3月31日以前に妊娠し、2022年4月1日以降に出産した方。
子育て応援金の対象は、2022年4月1日から2023年2月28日までに生まれた新生児の養育者です。なお、2023年3月以降に生まれた新生児の養育者は2023年度予算から支給されます。
2月1日(事業開始日)から申請受付が開始され、3月以降に順次支給される予定です。
この事業の特徴は、様々なニーズに即して必要な支援につなげる伴走型の相談支援と一体であることです。実施主体として、主に子育て世代包括支援センターなどが担います。
昨年11月に公明党は、子どもの幸せを最優先する社会の実現を目指す「子育て応援トータルプラン」を取りまとめ、伴走型相談支援の実施や「子ども家庭センター」の設置推進などを示しました。
さかのぼる2006年には、少子社会トータルプランを策定し、不妊治療の保険適用や幼児教育・保育の無償化などを実現してきました。
アメリカ実践哲学協会のルー・マリノフ会長は、現代社会の行き詰まりの原因は、「哲学の不在」にあると喝破しています。子育て支援にも一貫した哲学が必要です。
仁田まさとしは、子育てを全力で支援します。
ニッタ マガジン Vol.615 2023.01.02
中期計画が確定
2023年が始まりました。
横浜市は昨年の12月28日、インフルエンザ流行の始りを発表しました。流行開始の目安となる、1定点医療機関あたりの1週間の患者報告数1.00人を超え、2.61を示したことによります。この流行は3年ぶりとなりますが、新型コロナウイルス対策とともに有効な、丁寧な手洗い・消毒や必要な場でのマスクの着用、加湿器などを使った適切な湿度(50~60%)の確保などを宜しくお願い致します。
横浜市会の第4回定例会が昨年12月23日まで開かれ、今後4年間で重点的に取り組む政策をまとめた「横浜市中期計画(2022~2025)」が議決され計画が確定しました。この中には、公明党市議団が長年に取組んできた政策が取り込まれました。
2021年4月から選択制のデリバリー方式の昼食が学校給食法に位置付けられています。中期計画では、「デリバリー方式による供給体制の確保と生徒に満足してもらえる給食の提供に向けた準備を進める」とされ、2025年度までに「全員に供給できる体制の確保が完了」することが目標とされました。
中学校の昼食環境を整えるため、公明党市議団は1996年に「スクールランチ」の草案作りを始め、2012年度のモデル実施を経て、横浜型配達弁当が開始。2018年秋には「横浜型給食」を提案し、草案作りから25年を経て給食が実現しました。
全員に供給できる体制の確保には様々な課題があり、温かくより充実した給食に向けて不断の努力が必要です。
また計画には小児医療費助成について、2023年度中に中学3年生まで全額無料とすることも記されました。1992年に公明党市議団が市会で初めて提案して以来一貫して拡充を求めて来たものです。今後は18歳までの対象拡大を目指します。
仁田まさとしは、中学校給食と小児医療費助成の拡充を目指します。
ニッタ マガジン Vol.614 2022.12.26
わくわくする中学校給食メニュー
新型コロナウイルスの昨日の新規感染者数は、2,665名でした。
引き続き、手指の消毒や必要な場でのマスクの着用、効果的な換気などの基本的な対策、及びワクチン接種と検査キットの常備を宜しくお願い致します。
12月21日に、横浜市南公会堂で中学校給食メニューコンクールの表彰式が行われました。このコンクールは、中学校における食に関する指導及び中学校給食の推進を目指し、横浜市教育委員会事務局が2020年度より実施しているものです。
今年度は、4,121名の参加があり、優秀賞として10点、入賞作品として268点が選ばれました。
表彰式では、優秀賞を受賞した生徒を表彰するとともに、生活の課題解決に向けた献立作成にあたって、工夫したところやこれからの生活に生かしたいことなどのインタビューが行われました。
受賞者の皆様からは、「野球を頑張るために体を大きくしたいので、たんぱく質を取れるようにした」「汁気を少なくできるよう、ナムルにわかめを入れた」「肌荒れを防ぐために油分を取らないようにしたかったので、ゆでる献立をいれた」「冷めてもおいしい工夫をした」「午後眠くならないよう、血糖値が緩やかに上昇する工夫をした」「学習がはかどるよう、DHAを含む青魚を使った」など、献立に込めたたくさんの思いを聞くことができたと、所管課が記者発表で紹介しています。
優秀賞の中の5点は、23年度の中学校給食として提供される予定です。
2005年に食育基本法が施行され、2008年には学校給食法が改正されて学校給食の主な目的が栄養改善から食育に転換され、その役割も変化しています。
今後とも、中学校給食を通して食育が進むよう取組が求められます。
仁田まさとしは、中学校給食を充実し食育を進めます。
ニッタ マガジン Vol.613 2022.12.19
若年性認知症対策が拡充
審議中の横浜市補正予算では新型コロナウイルス感染症対策として、陽性高齢者ショートステイを2事業所準備し、自宅療養者への薬剤配送する薬局へ支援し、年末年始における診療体制を強化すること等が盛り込まれています。
引き続き、手指の消毒や必要な場でのマスクの着用、効果的な換気などの基本的な対策、及びワクチン接種と検査キットの常備を宜しくお願い致します。
65歳未満で発症する認知症を若年性認知症としています。その人数は、18歳から64歳までの人口における10万人あたり50.9人とされ、横浜市では約1,160人と推計されています。発症年齢の平均が51歳頃との調べも見られ、働き盛りでもあり仕事や家事が十分にできなくなるなど、本人はもとより勤務先や家族への影響が大きく、様々な問題が生じます。
若年性認知症の方への支援の充実を図るため配置されている若年性認知症支援コーディネーターが、12月から新たに市立大学附属病院認知症疾患医療センターに配置され、これにより市内でこれまでの認知症疾患医療センター(横浜ほうゆう病院、横浜市総合保健医療センター診療所、横浜総合病院)と合わせ4か所に配置されることになりました。
若年性認知症コーディネーターは、若年性認知症に関わる様々なご相談に応じており、居場所づくりや普及啓発などにも取り組んでいます。若年性認知症支援コーディネーターの配置により、個別相談や関係機関との連携が推進され、本人の状態に応じた適切な支援を受けられるように取組が進みます。
仁田まさとしは、認知症疾患支援に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.612 2022.12.12
バッテリーによる火災を回避
新型コロナウイルスの昨日の新規感染者数は2,009名と横ばいで推移しています。
引き続き、手指の消毒や必要な場でのマスクの着用、効果的な換気などの基本的な対策、及びワクチン接種と検査キットの常備を宜しくお願い致します。
このほど、横浜市資源循環局は、バッテリーの取り外せない充電式小型家電の出し方について、市民の皆様へのお願いを始めました。ニッタ マガジン Vol.603でご報告した実態と原因、そして今後の対応が前進しました。
コードレス掃除機、ロボット掃除機や手持ち扇風機などの充電式小型家電のバッテリーを原因とした収集車の火災が急増しています。
令和3年度の横浜市における収集車両火災件数は13件、そのうちバッテリーが原因とみられる火災は6件となっており、今年度は9件(9月現在)と既に前年度1年間を上回っている状況となっています。
バッテリーに使用されるリチウムイオン電池は、圧力や強い衝撃を受けると発熱・発火する恐れがあります。バッテリーを取り外せない小型家電は、生ごみ等と同じ袋に混ぜて出されて、収集車の中で押しつぶされることで火災が起きていると考えられます。
そのために資源循環局は、火災が起こらないよう、「バッテリーの取り外せない小型家電は、燃やすごみとは別の袋で『燃やすごみの日』に出してください」と呼びかけています。
また、30×15㎝未満の小型家電は、区役所等に設置されたピンクの回収箱に入れてリサイクルにご協力下さい。
11月24日(木)の横浜市公式LINEを通じて周知しており、今後は令和5年2月発行の「広報よこはま」に啓発記事が掲載される予定です。
仁田まさとしは、生活を支える廃棄物行政の推進に努力します。
ニッタ マガジン Vol.611 2022.12.05
レシ活VALUEが再開へ
2類から5類への議論や飲み薬「ゾコーバ」の報道など、次のフェーズへの移行が窺える新型コロナウイルスの昨日の新規感染者数は1,616名でした。
引き続き、手指の消毒や必要な場でのマスクの着用、効果的な換気などの基本的な対策、及びワクチン接種と検査キットの常備を宜しくお願い致します。
先週29日に開かれた横浜市会本会議において35億の補正予算が成立し、「レシートを活用した市民・事業者支援事業(通称:レシ活VALUE)」の追加実施が決まりました。
スマートフォンのアプリを活用して、飲食店やガソリンを除く市内事業者で発行されたレシートの利用金額に応じたポイント還元やキャッシュバックなどを行うことになります。
対象店舗は、店名、住所が記載されているレシートを発行できる市内事業者とし、今回はガソリンと飲食店は除きます。
還元額はレシート記載の利用金額の20%で、累積の上限額は、1人あたり1万2千円(利用金額としては6万円)、レシート1枚あたりの還元上限額は400円(利用金額としては2千円)としています。利用できる対象者は、市内居住者です。
この12月中には受託事業者(アプリ)を決定して令和5年1月1日から実施され、予算がなくなり次第終了となります。
スマートフォンを所持していない方を主な対象者としてレシートを郵送で受付けして銀行口座への還元を行う郵送受付分の増額も行われました。
対象店舗は同様ですが、令和4年12月31日まで発行のレシートが対象で、令和5年1月7日(1度のみ)までの受付となります。
還元額は利用金額の20%で、累積の上限は1人あたり3万円、食料品等のレシート1枚あたり上限600円、ガソリンは上限千円です。
仁田まさとしは、生活を守る経済対策に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.610 2022.11.28
施設の電気代等も補助を
昨日の、横浜市内における新型コロナウイルス新規感染者数は1,696名でした。
引き続き、手指の消毒や必要な場でのマスクの着用、効果的な換気などの基本的な対策、及びワクチン接種と検査キットの常備を宜しくお願い致します。
高齢者施設や障がい者施設では、介護サービス報酬などを基本に運営されており、急激な原油や物価の高騰による光熱費・燃料費、食材費の増加を利用者に転嫁することは困難です。
この状況を受けて、先に公明党神奈川県議団は黒岩祐治県知事に福祉施設への支援金の交付を緊急要望し、10月に県の補正予算が成立しました。11月9日(水)より、横浜市では市内の施設等を対象に、支援金の申請手続きが開始されています。
対象となる事業所は、令和4年10月1日時点で事業所を開設しており、令和5年3月31日まで事業を継続する横浜市内の施設や事業所とし、令和4年12月15日(水)まで申請可能です。
支援金額は、サービス種別ごとに異なりますが、
高齢分野では、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、訪問介護の施設・事業所、
障がい分野では、療養介護・施設入所支援、通所サービス、訪問系サービス等などとなります。(詳細は横浜市公式ホームページを参照下さい)
また、価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)や家計急変世帯に対しては、1世帯当たり5万円の支給手続きも始まっています。
仁田まさとしは、物価高騰対策に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.609 2022.11.21
第8波への備えを
このところの新型コロナウイルス新規感染者数は増加傾向にあり、さらなる感染拡大やインフルエンザとの同時流行も懸念されます。
先週17日には、横浜市新型コロナウイルス対策本部会議が開かれ、第8波に向けた対策が示されました。
第7波の時の課題を踏まえた検討の結果、救急と発熱外来に対策が必要として、第8波に向けた対策が次のように決定されました。
1.救急のひっ迫対策
軽症者からの要請による救急の出動件数が急増した経験から検討された対策
1)陽性高齢者の受入れとして、①陽性高齢者ショートステイ2施設(18人分)を設置し、退院支援ショートステイを23施設・36ベッドに拡大します。また、病床は1004床に拡充されています。
2)救急体制の充実として、予定されている救急自動車の納車時期を前倒して救急隊を84隊から96隊に拡充されます。
2.発熱外来のひっ迫対策
検査を受けたくても受けられない状況が生じた経験から検討された対策
1)コールセンターの140回線を180回線に増設するとともにホームページを改善し、相談体制の充実を図ります。
2)休日急患診療所の人員を増強して診療対策を強化し、医療機関の診療体制を確保します。
3)抗原検査キットを発熱外来の受診希望者、高齢者・障がい者・保護施設従事者、保育所の保育士等、小学校の教職員に配布し、高齢者施設の入所者にデュアルキットを確保します。
その上で市民に対して山中竹春横浜市長は、「早期のワクチン接種」と「各ご家庭への検査キットの常備」という日頃の備えを呼びかけています。
仁田まさとしは、第8波への対策強化を推進します。
ニッタ マガジン Vol.608 2022.11.14
早期の追加経済対策を
昨日の横浜市内における新型コロナウイルス新規感染者数は1,218名でした。
引き続き、手指の消毒や必要な場でのマスクの着用、効果的な換気などの基本的な対策を宜しくお願い致します。
このほど、公明党横浜市会議員団は山中竹春横浜市長に対して、下記の通り「経済対策に関する要望書」を提出し、スピード感をもって講じるよう強く要請しました。
(1)レシ活バリューの早期再開による物価高対策
早期再開の検討とともに、事業再開にあたってはより多くの市民が利用できるよう、利用者目線に立ったシステムの検討。
(2)子育て支援
①妊娠から出産・子育てまで一貫した伴奏型支援の充実、国による妊娠・出産時のそれぞれ5万円相当の支援にも伴走型施策を重視すること。
②国が検討している出産育児一時金の増額については、横浜市内の実情を踏まえた必要な支援の検討。
(3)中小企業支援
国の資金繰り支援、事業再構築や生産性向上と一体的に行う賃上げへの支援を推進。
(4)円安対応
円安メリットを最大限に引き出し市民へ還元するよう、観光活性化の推進。
(5)防災・減災対応ほか
激甚化・頻発化する自然災害を踏まえ、国の「防災・減災、国土強靭化のための5か年加速化対策」に基づく「流域治水」等の推進。ウクライナ避難民への越冬支援の実施。
(6)市民への周知
市民の理解が深まり広く効果が届くよう、わかりやすい周知。
山中市長は、「レシ活バリューは大事な事業」、「各要望内容を真摯に受け止め、市の補正予算や来年度予算案はもとより国へも要望する」と応じました。
仁田まさとしは、国と横浜市のネットワークで経済対策に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.607 2022.11.07
地域包括ケアシステムの情報プラットフォームを学ぶ
昨日の横浜市内における新型コロナウイルス新規感染者数は939名でした。
引き続き、手指の消毒や必要な場でのマスクの着用、効果的な換気などの基本的な対策を宜しくお願い致します。
所属している横浜市会健康福祉・医療委員会による福岡市行政視察報告(後編)です。
国では2025年を目途に、要介護の状態となっても住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を進めています。
その地域包括ケアシステムは、市町村が地域の自主性や特性に応じて作り上げていくことが求められています。
福岡市では、ICTを活用した地域包括ケアシステムの実現に向けて、①データ集約システム、②データ分析システム、③在宅連携支援システム、④情報提供システムからなる地域包括ケア情報プラットフォームを構築しています。
データ集約システムにより、行政・介護・医療・健康・生活支援のビッグデータを集約し約230種43億件のデータが蓄積されている(2022年9月現在)とのこと。
ライフログに基づく将来推計、経年比較による成果の確認、エビデンスに基づく成果指標の設定、地域における現状の見える化によるデータ分析システムで、科学的エビデンスに基づく施策の企画・立案と成果の確認・見直しによるCAPDサイクルを実現しています。
また、九州大学との連携でデータ分析を強化し、民間企業等のビジネスの創出に反映されています。
示唆に富む視察調査でした。
横浜市では、ICTを活用した地域医療連携ネットワークの構築を推進しています。
仁田まさとしは、地域包括ケアシステムの構築に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.606 2022.10.31
健康増進計画を学ぶ
秋も深まり間もなく迎えるこの冬は、過去2年間流行がなかったインフルエンザが、新型コロナウイルスと同時に流行する恐れがあり警戒が必要です。
引き続き、手指の消毒や必要な場でのマスクの着用、効果的な換気などの基本的な対策を宜しくお願い致します。
先週、所属している横浜市会健康福祉・医療委員会の行政視察が行われました。
その中で、福岡市を訪問して調査した特徴的な事項について2週にわたり報告します。
福岡市では、人生100年時代を見据え、誰もが心身ともに健康で自分らしく暮らせる持続可能な社会をつくるプロジェクト「福岡100』に取組んでいます。
例えば、市民の健康を阻害している要因の上位である「現役世代を中心として運動不足」を解消するため、自然と楽しく体を動かしたくなる仕組みがあるまちづくりに取組む「Fitness Cityプロジェクト」が始動しています。
具体的には、オフィスワーカーが集まる博多駅周辺をパイロットエリアに10月から次のような取組が行われています。
(1)上りたくなる階段
階段を上った回数を市内の名所の高さに見立てることで、階段の利用を促すようなデザインを試験導入。
(2)立ち寄りたくなる公園
健康イベントの開催やキッチンカーの誘致等、仕事の合間等で公園に立ち寄るきっかけづくり。
(3)歩きたくなる歩道
大博通りの西側歩道で「ひと駅分の歩きを促す、歩いて楽しい空間づくり」。
技術の進展や感染症の流行などの社会環境の変化、Well-Being重視やインクルーシブなまちづくりなどの新たな価値観の台頭を踏まえて、さらにこの「福岡100」を「何歳でもチャレンジできる未来のまちへ」に向けたステージへとアップデートしています。
仁田まさとしは、人生100年時代への備えに取組みます。
ニッタ マガジン Vol.605 2022.10.24
ワクチン接種間隔が短縮に
国の方針を受け、横浜市は先週20日に新型コロナワクチン接種間隔の短縮を発表しました。
ワクチンの種類は、ファイザー社ワクチン(BA.1対応型及びBA.4-5対応型)とモデルナ社ワクチン(BA.1対応型)があり、どちらも従来株に由来する成分とオミクロン株に対応する2種類を組み合わせた「2価ワクチン」と呼ばれるものです。
接種間隔が、これまでの「前回接種から5か月以上」より「前回接種から3か月以上」に短縮されます。
接種対象者は、従来のワクチンを2回以上接種した12歳以上のすべての方です。
短縮後接種間隔の適用日は、10月21日(金)以降の接種です。既に従前の接種間隔(5か月)で予約されている方で、短縮後の接種間隔に合わせて早く接種を受けたい方は、予約の取り直しが必要です。
今後、市から送付される接種券には、10月31日発送分までは、印刷の工程上、前回接種から5か月以降に接種できると記載されていますが、接種可能となる日は前回接種から3か月以降に変更となりますのでご注意ください。
また、新型コロナワクチンの特例臨時接種の実施期間は、令和5年3月31日までとされています。このため、追加接種を受けるためには、従来型ワクチンによる初回接種(=1回・2回目)を年内に完了する必要があります。接種されていない方は、積極的に接種をご検討下さい。
「専門家の間では、コロナに関してはかなり危機感がある。」(厚労省専門家会合 脇田座長)、「日本でもこの冬、かなり大きなコロナの感染拡大が起きるおそれがあるという認識を共有している。」(新型コロナ対策分科会 尾身会長)」との警鐘が鳴らされています。
仁田まさとしは、コロナ対策に全力で取り組みます。
ニッタ マガジン Vol.604 2022.10.17
保土ケ谷工場をEV充電基地に
横浜市は先週、オミクロン株(BA.4-5)対応ワクチンの接種を順次開始することを発表しました。個別接種は準備が整った医療機関から順次受付、集団接種は11月1日から接種を開始します。 コロナ感染予防のため、引き続き、手指の消毒や必要な場でのマスクの着用、効果的な換気などの基本的な対策を宜しくお願い致します。
資源循環局の決算審査報告の第3回目(最終回)です。
現在、ごみ焼却工場の保土ケ谷工場は休止中ですが、再整備の準備が進んでいます。
4月には地域向けの説明会が実施されました。そこでは、煙突から出るガスの影響を心配する声が多く、法令よりも厳しい基準による運用を求めました。局長からは、高性能な排ガス処理設備を導入することと、工場の運転にあたっては、国内トップクラスの排出基準を設けて適切に管理するとの考えが示されました。
また、大地震が発生した時には、既存の焼却工場では異常確認のために停止した焼却炉は、周辺が停電していると再稼働できませんが、保土ケ谷工場では長期間の停電時においてもごみの焼却と発電が継続できるよう大容量の非常用発電機を備えることが明らかとなりました。
横浜市は日産自動車と、電気自動車(EV)を活用した災害連携協定を結んでいます。EV車を移動式電源として地域防災拠点等に継続的な電源を確保・供給することが期待されています。
そのために、保土ケ谷工場の強みを活かし、災害時にもEV車に安定して充電を行う「充電基地」として活用すべきと提案しました。
副市長からは、工場敷地内にEV車の充電設備を設置する等の前向きな答弁を得ました。
仁田まさとしは、最先端の保土ケ谷工場を目指します。
ニッタ マガジン Vol.603 2022.10.10
小型家電の排出方法の周知を
先週、厚労省は新型コロナ感染の主流になっている「BA.5」に対応するワクチンを、今週13日から公的接種として開始する方針を示しました。
コロナ感染予防のため、引き続き、手指の消毒や必要な場でのマスクの着用、効果的な換気などの基本的な対策を宜しくお願い致します。
先週に続き、資源循環局の決算審査報告の第2回目です。
近年、ごみ収集中の車両火災が課題となっています。
令和3年度の横浜市における車両火災件数は13件、そのうちバッテリーが原因とみられる火災は6件であり、今年度はこれまで、車両火災件数は12件で、うちバッテリーが原因とみられる火災は9件と、既に前年度1年間の件数を上回っている状況が明らかとなりました。
燃やすごみに混入したリチウムイオンバッテリーがごみ収集車の中で発火し、火災につながるケースが増えている状況にあります。
そのバッテリーが使われている充電式家電はプラスチック製が多く、本来、区役所等にある「小型家電回収ボックス」に投函するか、バッテリーを取り外して「燃やすごみ」に出し、バッテリーは販売店や回収協力店に出すことになります。また、バッテリーを取り外すことができない小型家電については、同じく「小型家電回収ボックス」にリサイクルし、ボックスに入らない場合は収集事務所への持ち込みが呼びかけられています。
しかし、手持ち扇風機のような取り外せないものが燃やすごみに出され、火災につながる可能性を指摘し、利便性の高い排出方法を検討すべきと提案しました。
局長からは、バッテリーが取り外せない場合は、燃やすごみの日に単独で燃やすごみとは別の袋に入れて集積場所へ出せるよう、今年度中を目処に実施へ向け検討する考えが示されました。
仁田まさとしは、バッテリーの分別・排出方法の改善に努めます。
ニッタ マガジン Vol.602 2022.10.03
災害廃棄物処理の周知に工夫を
先週から、新型コロナと診断された方の医師による発生届けの対象患者が限定されています。①65歳以上、②妊婦、③入院が必要と医師が判断した方、④重症化リスクがあり、かつ新型コロナ治療薬の投与が必要な方が発生届出対象者となり保健所から連絡があります。該当しない方で陽性の方は「陽性者登録窓口」に登録して自宅で療養でき、「コロナ119」の電話番号や宿泊療養等のご案内があります。
コロナ感染予防のため、引き続き、手指の消毒やマスクの着用、効果的な換気などの基本的な対策を宜しくお願い致します。
令和3年度決算特別委員会が9月28日から行われており、翌29日の資源循環局審査で質疑しました。3週にわたって報告します。
先日の台風15号では、被害の大きかった静岡市内で災害廃棄物の課題が浮き彫りになりました。
横浜市の対応を質問したところ、横浜市にも支援の打診があり、質疑翌日には担当課長と係長を現地に派遣し、状況把握と必要な支援の検討を進める考えが示されたところです。
静岡市の事例に見るまでもなく、発災後の復旧・復興に向けて災害廃棄物への対応は重要なことです。
災害時のゴミの出し方は、①平時と同じ「生活ごみ」、②交通の妨げにならない場所へ出す「片付けごみ」、③業者が撤去を行う「災害がれき」に大別されます。
しかし、この分別や大災害の際の対応について知って頂いている市民の皆様は少ないのではないかと危惧し、市民への周知に力を入れて取組むべきと主張しました。
局長から、「効果的な周知方法について改めて検討していく」との考えが示されました。
仁田まさとしは、大規模災害時における破棄物対策に取組みます。
ニッタ マガジン Vol.601 2022.09.26
スクールランチから給食へ(下)
オミクロン株対応のワクチン接種について、本日より順次接種が始まります。
コロナ感染予防のため、引き続き、手指の消毒やマスクの着用、効果的な換気などの基本的な対策を宜しくお願い致します。
市立中学校の昼食環境を充実する取組みについて現在までを振り返る、まとめの章です。
平成29年1月に始まった横浜型配達弁当=ハマ弁の喫食率は当初1%と低迷しました。その後事業促進に向けて、当日注文の全校展開、LINEPayの導入、価格見直しなどが図られ、令和2年度末で7.3%となりました。
令和2年度には事業者との協定期間が終了することを踏まえ、平成30年秋に、公明党市議団はハマ弁を進化させた「横浜型給食」を提案しました。
この間の検討の中で例えば、ハマ弁推進校の仲尾台中学(中区)の視察で大きな示唆を得ました。ハマ弁への段階的移行を前提に、PTAと学校が協働で利用しやすい環境づくりに取組み、1年生では喫食率は80%となっていました。この視察でハマ弁を学校給食法に位置付けることが重要であると確認できました。
さらに、アンケートや外部有識者からの意見を参考に、市教委と議論を重ねました。
その結果、令和2年3月には市教委が令和3年度以降の方向性を、
〇ハマ弁の利用を促進し、家庭弁当や業者弁当も選べる選択制として食育の推進を図る。
〇ハマ弁のさらなる改善を図り、“できるだけ早期”に学校給食法上の給食に位置付けることを目指す。
と、示しました。
そして、令和3年4月より、選択制の中学校給食が始まり、喫食率は20%を超え順調なスタートを切りました。
草案作りに携わってから25年を経て横浜型中学校給食が実現しました。
仁田まさとしは、中学校の昼食環境の充実に努力を続けます。